朝が起きられない、体がだるくて学校に行けない――。
「怠けてるわけじゃない」とわかっていても、周囲の理解を得るのが難しい起立性調節障害(OD)。
子どもが中学・高校に通えなかったり、保健室登校や五月雨登校だったりすると、親としては「将来、働けるのだろうか」と不安になることもあるかもしれません。
この記事では、
- 起立性調節障害の症状は大人になるとどうなるのか
- 働けるようになる人の特徴やプロセス
- どんな働き方があるのか
- 実際の当事者の声
などを紹介しながら、「働くこと」について一緒に考えていきます。
答えは一つではありません。でも、選べる未来があることを知ってほしいのです。
起立性調節障害の子どもたち――「今」つらくても「未来」がないわけじゃない
起立性調節障害(Orthostatic Dysregulation/OD)は、自律神経のバランスが崩れ、特に午前中に起きられない、めまい、頭痛、倦怠感などが出る病気です。
思春期に発症しやすく、学校に行けなかったり、遅刻や欠席が増えたりすることが特徴です。
中には「甘えでは?」という偏見もあり、親子ともに孤独な思いを抱えることがあります。
でも、今この瞬間つらくても、「ずっとこのまま」と決まっているわけではありません。
「今できないこと」は、「未来もできないこと」とは限らないのです。
大人になったら治るの?――症状の経過とその後
起立性調節障害は、成長とともに症状が軽快していくケースが多くあります。
日本小児心身医学会の調査でも、高校卒業頃から改善する子が増えるという結果が出ています。
ただし、大人になっても症状が続く「POTS(体位性頻脈症候群)」などへ移行することもあり、症状の有無には個人差があります。
つまり、「治る人もいれば、症状と付き合いながら生活する人もいる」ということ。
大事なのは、「体調が完全に良くなったら働ける」ではなく、「体調に合わせた働き方がある」という視点です。
不登校・中退でも働ける?――学歴や経歴よりも大事なこと
学校に行けなかったからといって、将来に進めないわけではありません。
たしかに、学歴があると選べる職種は増える傾向はありますが、それ以上に大切なのは「自分に合った環境を見つけること」「無理せず力を発揮できる形を探すこと」です。
そのための選択肢も増えてきました。たとえば、
- 通信制高校や高卒認定を活用し、マイペースで学ぶ
- 自分の得意を伸ばし、仕事につなげる(イラスト・動画・プログラミングなど)
- 働く前に「準備をする」支援制度を活用する
なかでも、「就労準備支援」や「障害者就労支援」は、体調や特性に合わせて一歩ずつ社会参加を目指すための仕組みです。
たとえば、以下のような支援があります:
- 就労移行支援事業所:18歳以上の障害や体調に配慮が必要な方が、2年間の支援期間の中で職業訓練や就職活動を行える福祉サービス
- 地域若者サポートステーション:学校や職場に馴染めなかった若者向けに、個別相談や職業体験を提供
- オンラインスクールや在宅ワーク支援:通所が難しい人に向けた新しい支援形態
こうした「準備のための時間」を経て、自分に合った働き方を模索していくことができます。
どんな働き方があるの?――“体調に合わせて選ぶ”という視点
起立性調節障害を抱える人の働き方に、正解はひとつではありません。大切なのは「体調に合わせたリズムを尊重できるか」です。
たとえば、以下のような仕事や働き方が挙げられます。
- フレックス勤務や午後始業が可能な職場
- 完全在宅やリモートワーク(文章・デザイン・事務補助など)
- 短時間・週数回からの勤務(パート・アルバイト含む)
- 自営・フリーランスとして自分のペースで働く
最近では、クラウドソーシングやスキルシェアを通じて、在宅でできる仕事の選択肢も広がっています。
体調に合わせた働き方の分類を図に示します。
| 出社中心 | 在宅中心 | |
|---|---|---|
| 自由度が低い | 通常のフルタイム正社員(固定時間・出社) | 在宅勤務の正社員(時間固定) |
| 自由度が高い | シフト制アルバイトパート勤務 | フリーランス/クラウドソーシング/在宅ワーク |
また、就職せずに「好きなことを続ける」ことが、いつの間にか仕事になっていた、というケースもあります。
進路を焦らず、「今の自分でもできそうなこと」から始めてみることが一歩になります。
実際に働いている当事者の声
「実際に働いている人って、どんなふうにやっているの?」
そんな疑問に応える、当事者のリアルな声も紹介します。
• Aさん(40代女性)
「子供のころから朝が弱く、なんとか学校に行っても横になっていました。今は在宅を中心に外資件企業で経理の仕事をしています。長い月日がかかりましたが朝の弱さを立て直すことができたので、脳の疲れていない朝方に仕事をしています。自分のペースを大事にしています。」
▶︎ 体験談全文はこちら(POTS and Dysautonomia Japan)
• Bさん(20代男性)
「小学校高学年の頃にODを発症し、通信制高校から専門学校を経て、現在、救急救命士として働いています。」
▶︎体験談全文はこちら(EduA)
こうした声を知ることで、「自分にも道があるかも」と感じられるきっかけになるかもしれません。
家族にできること――「社会につながる力」を育む関わり方
子どもが学校に行けない状態にあると、親としては焦ったり不安になったりするのが自然です。
でも、「今の状態を否定しないこと」「本人の気持ちを受け止めること」から始めてみてください。
家での過ごし方や趣味の時間が、実は「社会とつながる力」を育てる大切な時間になることもあります。
ゲーム、絵、動画、ものづくり……好きなことを通じて「得意」を育むことは、将来の可能性を広げていきます。
そして、家族が抱え込みすぎず、カウンセラーや支援者に相談することも、とても有効です。
まとめ――「今は難しい」からこそ、未来をあきらめないで
起立性調節障害の子どもたちは、たしかに今、学校に行くことや社会に出ることが難しいかもしれません。
でも、「今できないこと」は、「これからもできないこと」とイコールではありません。
症状が和らぐ人もいますし、和らがなくても「付き合いながら働く」方法はたくさんあります。
大切なのは、「自分に合ったスタイルを探すこと」。
そして、焦らず、自分のペースで歩んでいくことです。
もし、今の不安を誰かと共有したいなら
進路のこと、働くこと、子どもの将来のこと――
一人で考え続けるのは、とても大変なことです。
当相談室では、起立性調節障害のお子さんや保護者の方のための個別カウンセリングを行っています。
小さな疑問からでも大丈夫。
お話を伺いながら、一緒に未来を見つけていけたらと思っています。
▶︎ [個別カウンセリングの詳細はこちらへ]
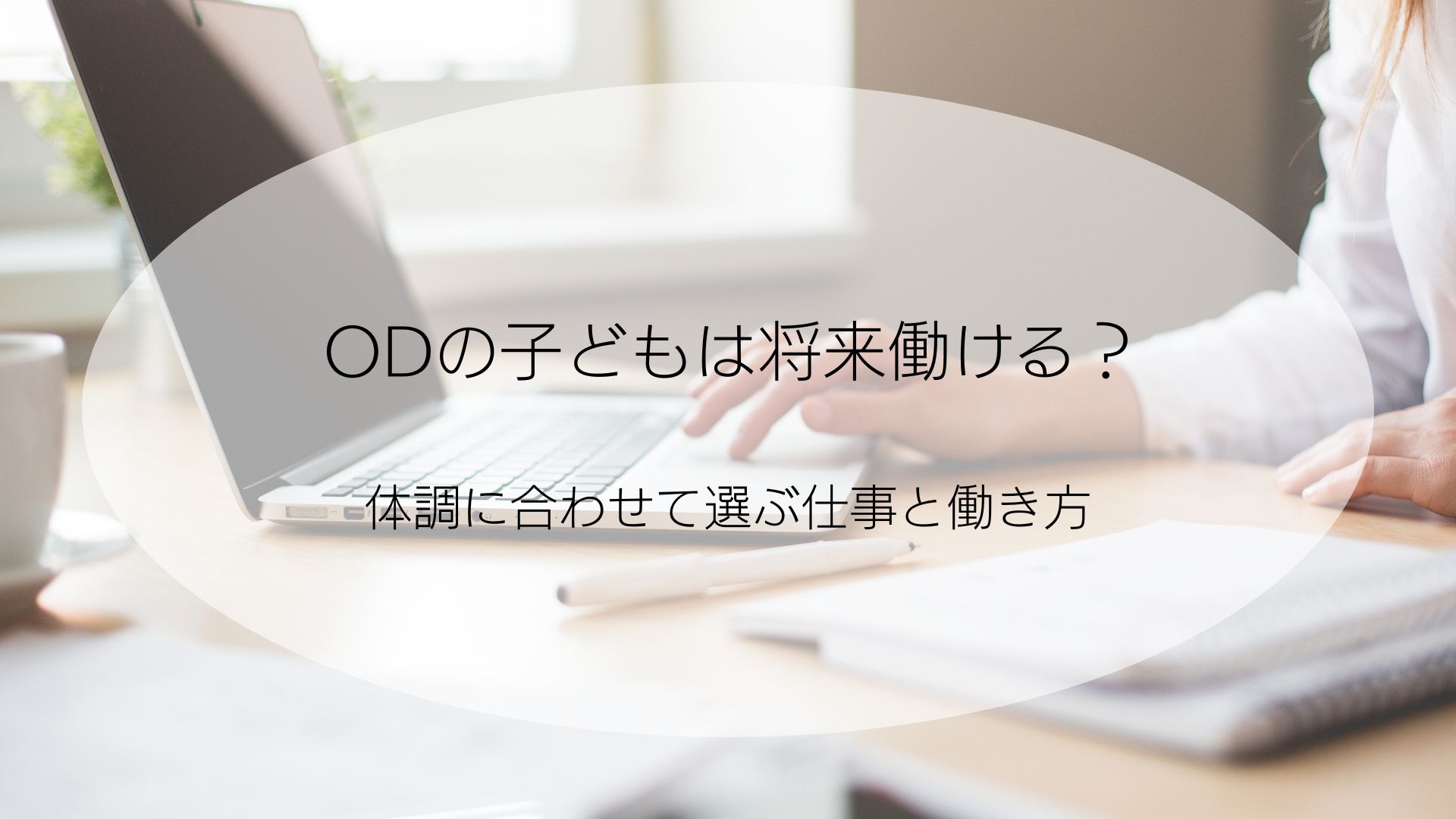


コメント