はじめに
「ねぇ、ぎゅーっとして」
そう言って、小学生の子どもがそっとこちらに近づいてくるときがあります。
抱きしめると、ふっと力が抜けたように表情がゆるみ、心がほどけたような顔を見せる。
そしてしばらくすると、何かをチャージしたかのようにすっと背を向け、しゃんとした背中でまた歩き出していく――。
この何気ないやり取りの中に、子どもの心の発達と、親子の信頼関係の本質がぎゅっと詰まっています。
母親や父親が子どもを「抱きしめる」こと。
それは、愛情を伝える行為であると同時に、子どもの心に安心を与え、挑戦する勇気を育てる大切な関わりなのです。
小学生の「ぎゅー」に詰まった心のサイン
ある日の朝、学校に行く準備をしながら、どこか元気のない表情をしていた小学生のわが子。
何か言いたそうで、言葉にはしないけれど、ふと近づいてくる。
「ぎゅーってしてほしいのかな?」と思って腕を広げると、照れくさそうに、でもうれしそうに飛び込んできました。
その瞬間、子どもの身体から緊張がほどけていくのが伝わってきます。
心の奥にあった不安やもやもやを、体ごと受け止めるようなひととき。
そして数十秒後、子どもは何も言わずにすっと背を向け、「いってきます!」と元気に出発していきました。
その背中には、確かな自信が宿っていました。
親の胸の中で得た安心感が、そのまま「がんばってみよう」という心の力に変わっていったのです。
オキシトシンとは?ぎゅーで生まれる安心の化学反応
「ぎゅーっとする」ことで、脳内ではオキシトシンというホルモンが分泌されます。
オキシトシンは「愛情ホルモン」や「絆ホルモン」とも呼ばれ、触れ合いやスキンシップを通して分泌が促進されます。
このホルモンには以下のような作用があります:
- 不安やストレスを和らげる
- 信頼感や安心感を高める
- 自律神経のバランスを整える
- 社会的なつながりや共感性を高める
子どもが不安を感じているとき、「どうしたの?」と聞くよりも、まず抱きしめてあげる。
それだけで、オキシトシンが分泌され、子どもの心が落ち着き、次の一歩を踏み出す準備が整っていきます。
発達段階から見る「スキンシップ」の重要性
◇ 乳児期
この時期は、スキンシップがすべての基礎。
母親や父親に抱かれることで、「自分はここにいていい存在なんだ」という感覚が育まれます。
◇ 幼児期~学童期
この時期の子どもは、“「自立」と「依存」”を行ったり来たりしています。
見た目にはもう「甘えん坊」を卒業したように見えるけれど、実は心の中にはまだまだ「ぎゅーっとされたい気持ち」が残っています。
大きくなってきたからこそ、子どもは無意識にそれを隠そうとしたり、照れ隠ししたりします。
でも、ときどきふとした瞬間に、「ぎゅー」してもらいたい気持ちがあふれてくる。
そのときに親がそれを受け止めてあげることで、子どもは安心し、心が回復していきます。
起立性調節障害と「抱きしめる関わり」
起立性調節障害(OD)は、自律神経のバランスが崩れることで、朝起きられない、立ちくらみや頭痛がある、学校に行けないといった症状が現れる病気です。
心と体の両面に負荷がかかるこの障害は、本人も親も苦しさを感じやすいもの。
そして、見た目には「サボっている」「やる気がない」と誤解されがちです。
そんなときこそ、親が「安心できる存在」としてそばにいてあげることが、何より大切です。
「学校行けないんだね」「つらいね」――そう言葉をかけながら、抱きしめる。それだけで、子どもの心には「このままの自分でいい」という感覚が広がります。
特に起立性調節障害の子どもたちは、「がんばれない自分」を責めていることが少なくありません。
その心に届くのは、言葉よりも、温かい抱擁かもしれません。
安全基地とは?愛着理論で見る「ぎゅー」の力
愛着理論の創始者ジョン・ボウルビィは、親との安定した関係を「安全基地(secure base)」と表現しました。
子どもは、安全基地を確認できているからこそ、外の世界へ冒険しに行けるのです。
つまり、“「ぎゅーっとして」→「安心を得る」→「自信をもって前へ進む」”というプロセスこそが、心の発達そのものなのです。
忙しくてもできる1分スキンシップのすすめ
日々の生活は忙しく、子どもの要求すべてに応えていくのは難しいと感じることもあります。
でも、「ぎゅーっとする」だけなら、ほんの1分でも十分です。
それは、子どもにとっては言葉を超えた安心であり、親にとっても、「私ができることがまだある」という小さな自己肯定感につながっていきます。
抱きしめる余裕がないときこそ、親自身をいたわって
「抱きしめてあげるのが大事」とは分かっていても、いつも余裕をもって接するのは、正直むずかしい――そう感じている方もいるのではないでしょうか。
怒ってしまったあとに自己嫌悪になることもあるし、自分の心がいっぱいいっぱいで、抱きしめる余裕なんて持てない……そんな日もあるかもしれません。
でも、完璧じゃなくていいのです。
大切なのは、「もう一度ぎゅーっとしてみようかな」と思える気持ちです。
小さな関わりの積み重ねが、やがて子どもにとっての安心感と信頼につながります。
そして、「自分自身もまた、誰かに抱きしめられたかった」と気づくことがあるかもしれません。
それも、とても自然なことです。
まとめ:ぎゅーっとして、また歩き出す
「ぎゅーっとして」は、子どもからのSOSであると同時に、「ここでエネルギーを充電したら、またがんばれるよ」という心のメッセージでもあります。
特に、起立性調節障害や、心が揺らぎやすい時期の子どもたちにとって、親の腕の中は、社会という荒波の中で帰れる「港」のような存在。
一人でがんばらなくてもいい。
でも、がんばれるときには、ちゃんと前に進める。
その信頼と勇気を与えてくれるのが、「抱きしめる」というシンプルで深い行為です。
どうか、今日一日がんばったわが子を、そっと抱きしめてあげてください。
あなたのぬくもりが、きっと、子どもの明日の力になることでしょう。
ご相談・カウンセリングのご案内
「ぎゅーっとしてあげたい。でも、うまくできない。」
「この子にどう関わればいいのか、わからなくなる。」
そんなときは、ひとりで抱え込まずにご相談ください。
当カウンセリングルームでは、起立性調節障害など子どもの不調や育児の悩みを抱える保護者の方に向けて、カウンセリングや対話のサポートを行っています。
親が安心できる場所があってこそ、子どもにも安心が伝わります。
あなたの気持ちを、まずは話してみませんか?
あなたの一歩をお増しております。
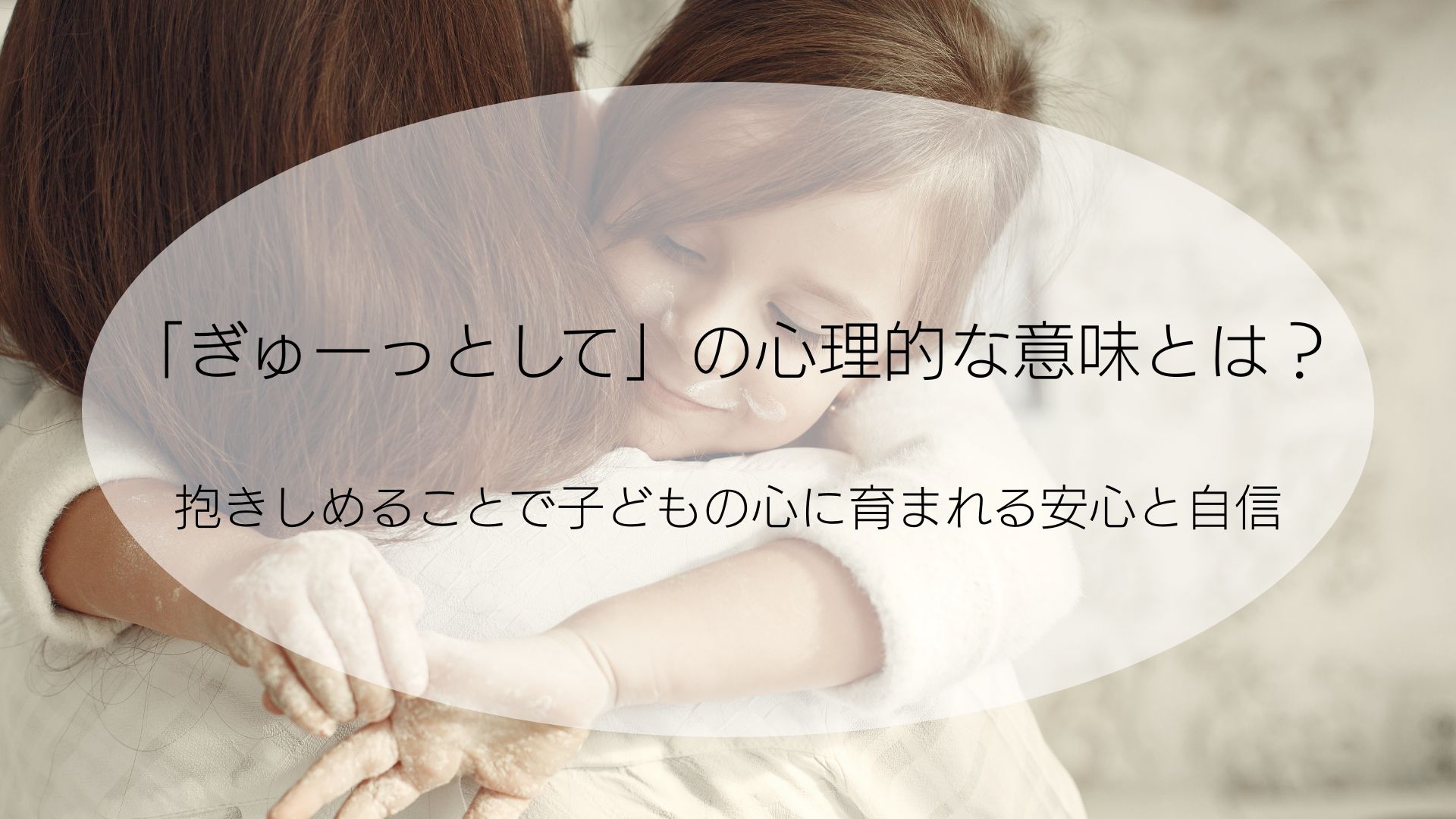


コメント