はじめに
「このまま一日中ゲームやネットばかりで大丈夫なのだろうか」
「取り上げた方が、子どものためになるのでは…」
不登校のお子さんを見守るなかで、親としてこんな不安を抱いたことはありませんか?
学校に行けないことに加えて、家ではゲームやスマホ漬け。見ている親はつらく、どうにかしなければという気持ちになるのは当然です。
(当事者の親である私も同じ気持ちです・・・)
けれども、精神科医や心理の専門家は口をそろえて言います。
「ゲームやネットをただ取り上げることは、子どもをさらに追い詰めてしまう危険がある」と。
精神科医の村上 伸治(むらかみ・しんじ)先生は、プレジデントオンラインの記事(Yahoo!ニュース掲載はこちら)で次のように語っています。
「不登校の子どもからゲームやネットを取り上げるのは、海で溺れている子がワラにもすがる思いでしがみついている丸太を取り上げるのと同じ」
この言葉には、子どもを理解するための大切な視点が含まれています。
この記事では、その理由を整理しつつ、親としてどんな関わり方ができるのかを一緒に考えていきましょう。
ゲーム・ネットは「逃げ場」でもあり「丸太」でもある
不登校の子どもにとって、ゲームやネットは単なる娯楽ではありません。
- 学校に行けない自分を責める気持ち
- 周囲との関係が途切れた孤独感
- 体調が思うようにならない不安
そうした感情から一時的に解放される「逃げ場」であり、同時に「つながりを保つ手段」でもあるのです。
精神科医の村上 伸治先生は、「ゲームを取り上げるのは、海で溺れている子がワラにもすがる思いでしがみついている丸太を取り上げるのと同じ」と表現しました。
苦しさの真っただ中にいる子から、唯一の支えを奪うことは、さらに深い孤立や絶望につながりかねません。
- 学校に行けないことで失われた「居場所」を補う
- 同じ趣味の仲間とつながれる
- 日常の不安や孤独を和らげる
これらは子どもの心のバランスを保つ上で大切な役割を果たしています。
親が取り上げたくなる気持ちの背景
一方で、親が「取り上げたい」と思ってしまうのも自然です。
- 学校に行けないのに遊んでばかりに見える
- 昼夜逆転が進むのではないか
- 将来のことが心配
こうした不安から「制限した方がいいのでは」と考えてしまいます。
取り上げが生む“負の連鎖”
しかし、親の「心配だからこそ」という気持ちが裏目に出ることもあります。
• 信頼関係が崩れる
→「どうせ自分の気持ちはわかってもらえない」と子どもが心を閉ざす。
• 逃げ道を失い、自己否定感が強まる
→「自分はダメだ」という思い込みが固定化。
• 反発や家庭内不和が増える
→親子で衝突が増え、家庭が安心の場でなくなる。
こうした悪循環に陥ると、ますます回復の道のりが遠ざかってしまいます。
起立性調節障害(OD)との関連性
起立性調節障害のお子さんの場合、ただでさえ「朝起きられない」「体調が安定しない」といった身体的ハードルがあります。
これは怠けや気持ちの問題ではなく、自律神経の不調によるものです。
そのため、学校に行けないこと自体に大きな罪悪感を抱えやすく、自己肯定感が下がりやすい特徴があります。
そんなときにゲームやネットは、「自分が存在できる場所」「達成感を得られる場」となることがあります。
親としては「依存が進むのでは」と不安になるでしょう。けれども、それを頭ごなしに奪うことは、心身の回復をさらに妨げる可能性があるのです。
親ができる具体的な関わり方
雑談を大切にする
不登校はその理由が本人にもよくわからないことが対応を難しくさせています。
対応の基本は、自分の気持ちに気づいて言葉にする能力を育てること。
思っていることを言葉にする訓練として最も手軽で効果があるのは雑談です。
雑談のコツは助言を一切しないことです。
助言をすると指導になってしまい、雑談ではなくなってしまいます。
親子の雑談が豊かな家庭では、不登校は起こりにくく、起きたとしてもこじれにくくなります。
親がイライラしていたり、不登校を責める雰囲気があると雑談は生まれません。
親との雑談が豊かになると、親の対応に問題があれば、本人が気軽に文句を言えるようになります。
なので、親が良かれと思って本人に害を及ぼすことが減るでしょう。
気軽に話ができる関係性を築くことを普段から心掛ける…ここが肝なのです。
一方的に禁止せず、話し合いでルールを決める
「〇時間までにしよう」「夜は〇時以降は控えよう」といったルールは、親子で相談して決めるのがおすすめです。
子どもが納得して参加したルールなら、守りやすく、信頼関係も壊れません。
代わりの「安心できる居場所」を
学校に行こうが行くまいが、自分は親に愛されていると感じられる環境で十分休めた子には、エネルギーが充電されます。
十分に充電された子は、勝手に何かを始めます。
- 趣味(絵、音楽、手芸など)
- 外の空気を少し吸える散歩
- 家族のためになること(料理など)
「ゲーム以外でも安心できる場」を少しずつ広げていくと、結果的に依存も和らいできます。
逆に、ゲーム等から離れられない場合は、本人が周囲から責められる状況が続いていたりします。一つのバロメーターになるでしょう。
小さな“できたこと”を積み重ねる
「今日は朝10時に起きられた」
「昨日より長く机に向かえた」
「短時間だけ外出できた」
こうした小さなステップを認めてあげることが、次の一歩への力になります。
外部の支援を取り入れる
親子だけで抱え込むと、親の心も疲弊します。
カウンセラー、スクールカウンセラー、親の会など、外の力をうまく使いましょう。
子どもの一番の願いは「普通にして欲しい」
不登校の子に「親にどうしてもらいたい?」と尋ねると「普通にしてほしい」と言うそうです。
その「普通」とは、
- 学校へ行っていた時と同じように接してほしい
- 登校しようがしまいが同じように愛してほしい
ということです。
不登校をなくす努力を止め、学校に行こうと行くまいと親子関係をどう豊かにするかを親子で話し合えるようになると、敵対していた親子が同じ方向に向かって歩み始めるでしょう。
親自身のケアも忘れずに
子どもを思う気持ちが強いほど、親は「何とかしなければ」と自分を追い詰めがちです。
でも、親が疲れ切ってしまうと、子どもはもっと不安になります。
- 同じ悩みを持つ親とつながる
- 相談機関に話してみる
- 自分の休息の時間を確保する
「親の安心」が、親子関係の豊かさにつながり、子どもにとって一番の安全基地を作ることになる。
このことを心に留めておいてほしいなと思います。
まとめ:取り上げるのではなく、共に歩む
不登校やODのお子さんにとって、ゲームやネットはときに「心をつなぐ命綱」になります。
それを取り上げるのではなく、親子関係の豊かさに目を向け「安心の居場所を広げていくプロセス」に付き合うことが、親にできる大切な支え方です。
「禁止」よりも「信頼」
「取り上げる」よりも「共に歩む」
この視点を心にとめて、お子さんとの関わり=普通に接する(愛する)ことを続けてみてください。
ご相談・カウンセリングのご案内
まずは親である私が元気でいたい!
そう思っていらっしゃる方もおられると思います。
元気でいるためには、今抱えている気持ちを吐きだすこと、その吐きだした気持ちを受け取ってもらうことが大切です。
一人で抱え込まずにご相談ください。
当相談室では、当事者でもあるカウンセラーが、実体験も交えてあなたに寄り添います。
お気軽にご相談ください。
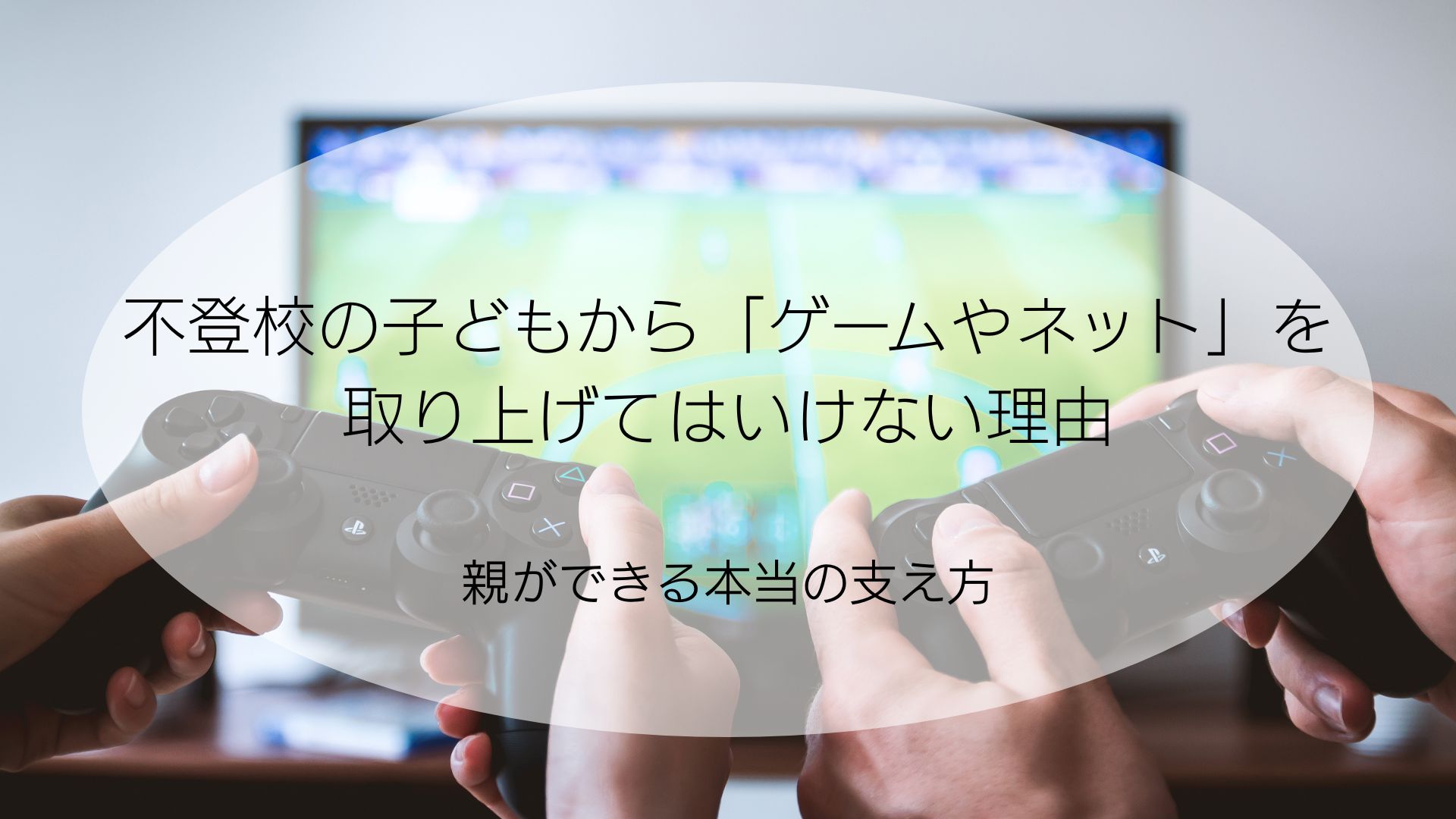


コメント