「中学校はなんとか卒業できたけれど、高校ってどうしたらいいのだろう?」
OD(起立性調節障害)の症状を抱えながら、そんな不安を抱える中学生・保護者は少なくありません。朝なかなか起きられず、登校時間帯を無理すると体調が崩れる。そんな状況では「普通の全日制高校に行けるのだろうか」「遅刻や欠席が増えたらどうしよう」という悩みが尽きません。
しかし、安心してください。ODの子どもでも通いやすい高校の選び方があります。
多様な通学スタイルや支援体制がある高校を知ることで、「自分(子ども)らしい高校生活」を見つける第一歩となります。
本記事では、ODの症状・特徴をふまえたうえで、全日制・定時制・通信制の高校それぞれのメリット・注意点、選ぶ際のポイント、保護者としてできる支援を整理していきます。
起立性調節障害とは?高校進学にあたって知っておきたいこと
まず、ODの子どもが高校進学を検討する際に理解しておきたい「どのような状況になるか」を整理しましょう。
ODでは、朝起きるのがつらい・立ちくらみ・倦怠感・頭痛などの症状がみられ、中学生・高校生に多く見られます。
特に「午前中に体調が悪く、午後になると少し回復する」という傾向もあるため、登校日・通学時間・授業時間帯などが通いやすさに大きく関わってきます。
また、症状により遅刻・欠席・途中退席が多くなりがちで、高校では出席日数・遅刻回数などが卒業・進級に影響を及ぼすケースもあります。
つまり、高校選びを考える際には「体調に配慮した通学ペース・登校時間・学校支援があるか」を軸に考えることが、ODの子にとって重要です。
高校のタイプ別メリット・注意点
高校は大きく「全日制」「定時制」「通信制」の3種類があり、それぞれ通いやすさ・支援体制・学習ペースに違いがあります。ODの視点から、それぞれを比較してみましょう。
全日制高校
メリット
- 通常のカリキュラムで学び、進学・就職ともに選択肢が多い。ODの子にとって「普通の高校生活を送りたい」という思いに応えやすい。
- たくさんの友人・クラブ活動の機会・対面授業で学びやすい環境。
注意点
- 朝早くに登校することが多く、定刻通りに起きるのが難しいODの子にとっては負担が大きくなりがちです。
- 遅刻・欠席が多いと進級・卒業に支障をきたす可能性があります。ODの症状で出席日数を確保できない場合、全日制ではリスクが生まれます。
- 学校側・先生側の支援・配慮が整っていないと、「怠けている」と誤解されてしまう場面もあり、ストレスになることがあります。
定時制高校
メリット
- 授業開始時間が午後から、または夕方から始まる学校もあり、朝起きるのが苦手なODの子にとって登校しやすい仕組みがあります。
- 少人数・個別支援が整っている学校も多く、ペースをゆるめて学び直しやすい環境があるという報告があります。
注意点
- 授業時間帯・通学時間・通学回数などが全日制と異なり、クラブや部活・学校行事が少ない、または内容が異なる場合があります。
- 通常の高校入試で出願する場合、定時制・通信制の性格を事前によく理解して志望校選定する必要があります。
通信制高校
メリット
- 自宅学習・オンライン授業・スクーリング(登校日)といった柔軟な通学スタイルが特徴で、午前中起きられない・体調不安定なODの子にとって通いやすい選択肢です。
- 登校日数が少ない場合(例:年間20日程度)という学校もあり、体調を見ながら無理なく学び進められます。
- ODの子どもを受け入れている学校・コース例も複数紹介されており、体調に配慮したカリキュラム・相談体制が整っているケースがあります。
注意点
- 進路先(大学・専門学校・就職)を意識するなら、自己管理能力・自宅で学ぶ習慣が必要です。体調管理+学習習慣の両立がカギになります。
- 一人で学習する時間が多くなるため、 引きこもりにならないよう学校・家庭・支援機関でフォローが必要です。
- 通信制・定時制は「高校卒業資格」が取得できるとはいえ、学校・コースによって「進学支援」「学び直し支援」の充実度に差があります。
例として「進路指導が手厚い」「レポート・スクーリングの代替がある」学校を選ぶことが大切です。
高校選びの際に確認したいポイント
ODの子どもが高校を選ぶ際、以下のような観点で学校を見ていくと、通いやすさ・学びやすさが高まります。
登校時間・通学時間・出席要件
- 朝起きるのがつらい・午前中調子が出ないというODの特性をふまえて、「何時から登校か」「遅刻・早退にどう対応してくれているか」を聞きましょう。
- 通学距離・通学手段も重要です。通学そのものが体調負担になることがあります。例えば長時間バス通学・乗り換えが多い道などは負荷になります。
- 出席日数・授業時数・評価基準(内申・進級・卒業)をあらかじめ確認しておくことが重要です。ODで欠席・遅刻が多くなった場合の影響を知っておくことで安心材料になります。
学校のサポート体制・理解度
- 学校側に「ODという病気を知っているか」「遅刻・早退・出席不良への対応実績があるか」などを確認しましょう。例えば、保健室登校やオンライン授業・補講などの制度があるか。
- 担任・保健教諭・スクールカウンセラーなどが体調不良・登校困難への配慮をしてくれる環境かどうかもポイントです。
- 見学時・個別相談時に「うちの子の体調の場合どうなりますか?」と聞けると、子ども本人・保護者双方がイメージをつかみやすくなります。
学び方・進路支援・学習環境
- 通信制・定時制を選ぶ場合、自宅学習・オンライン授業・レポート・スクーリングなどどういう仕組みかを確認しましょう。ODの体調ペースに合わせて無理なく学べる環境があるかが鍵です。
- 進路指導・学び直し支援・資格取得支援などが充実している学校であれば、将来の選択の幅が広がります。ODの症状があっても「進学したい」「専門をめざしたい」といった希望を持てることが大切です。
本人の“通えそうか”を一緒にシミュレーション
- 保護者・子どもで「無理なく起きられる時間帯」「通学して体調が安定している時間帯」「休みがちになったときどうしたらいいか」を話し合っておくとよいでしょう。
- 学校の体験・見学・説明会に参加し、実際の登校時間・雰囲気・サポート体制を体感することがおすすめです。学校案内だけでなく、在校生・卒業生の声が聞けるならさらに安心材料になります。
- 「無理をして通学して症状が悪化してしまったら元も子もない」という視点を忘れずに、「安心して通えるかどうか」を重視する姿勢が大切です。
学費と支援制度もチェックしておこう
高校を選ぶ際に、学費や通学費用の見通しを立てておくことも大切です。とくに通信制・私立高校を検討する場合、公立よりも授業料や教材費が高くなる傾向があります。
■ 公立高校の目安
- 全日制(公立):授業料は年額約12万円前後(※2025年度時点での標準額)。
- 定時制(公立):授業料は1単位あたり約330円。年間10〜15万円程度が目安です。
- 教材費・制服・交通費を含めると、年間20万円前後が平均的です。
■ 私立・通信制高校の目安
- 私立全日制:授業料は年間40〜70万円前後が多く、入学金や施設費を含めると初年度は100万円を超えることもあります。
- 通信制(私立):登校日数やコースによって幅がありますが、年間20〜50万円程度が一般的です。サポート校を併用する場合は別途費用がかかります。
こうした学費負担を軽減するために、国や自治体の支援制度を活用することができます。
高等学校等就学支援金制度(国の制度)
すべての高校生が対象となる授業料支援制度で、所得に応じて授業料の一部または全額が国から支給されます。
- 対象:世帯年収約910万円未満(目安)
- 支給額:公立高校では授業料が実質無償、私立高校では年収に応じて年額約39万6,000円まで支給(都道府県によって上乗せあり)
- 手続き:入学時に学校を通じて申請
通信制・定時制・私立高校も対象となるため、学費が理由で進学をためらう必要はありません。詳細は各都道府県の教育委員会・学校窓口で確認を。
参考:文部科学省「高等学校等就学支援金制度」
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/
自治体の上乗せ支援・授業料軽減補助
都道府県によっては、国の就学支援金に加えて独自の「授業料軽減助成」や「入学金補助」「通学費助成」を行っています。
例)東京都では、
- 私立高校授業料軽減助成金(最大約61万円)
- 通信制・定時制高校向け補助制度
があり、実質的に授業料が無償に近い場合もあります。
通学定期・交通費の支援、制服・教材費の助成なども自治体によって異なるため、「〇〇県 私立高校 就学支援金」「通信制 高校 補助」などで調べておくと安心です。
奨学金や教育ローンも視野に
- 日本学生支援機構(JASSO)奨学金:高校生も対象の予約型奨学金(進学後に支給)があります。
- 自治体・民間奨学金:病気・障害・不登校経験のある子どもを対象にした奨学金もあります。
- 教育ローン:日本政策金融公庫の「教育一般貸付(国の教育ローン)」なども利用可能です。
家庭の負担を軽くしつつ、子どもが安心して学び続けられる仕組みを整えておくことが、進学後の安定にもつながります。
高校別・年間学費の比較(2025年度目安)
| 区分 | 授業料(年間) | 初年度費用(入学金・施設費等含む) | 教材・制服・交通費等 | 年間合計の目安 | 就学支援金の対象 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公立高校(全日制) | 約12万円 | 約20万円 | 約8〜10万円 | 約30〜40万円 | ◯(年収約910万円未満で実質無償) |
| 公立高校(定時制) | 約3〜5万円(単位制) | 約10万円 | 約5〜8万円 | 約20万円前後 | ◯(支給あり) |
| 私立高校(全日制) | 約40〜70万円 | 約30〜50万円 | 約10〜15万円 | 約70〜120万円 | ◯(最大約39.6万円+自治体上乗せ) |
| 通信制高校(公立) | 約3〜5万円 | 約5万円 | 約2〜5万円 | 約10〜15万円 | ◯(支給あり) |
| 通信制高校(私立) | 約15〜40万円 | 約10〜20万円 | 約5〜10万円 | 約30〜70万円 | ◯(支給あり・自治体補助あり) |
ポイント
- 私立や通信制でも、高等学校等就学支援金制度の対象となるため、世帯年収によっては実質無償化または大幅軽減されます。
- 特に東京都などは、独自の「授業料軽減助成」を実施しており、国の「高等学校等就学支援金」と合わせて、都内私立高校平均授業料相当額まで支援されるようです。
- 通信制高校では「登校日数・コース・サポート校利用の有無」により費用差が大きくなるため、学校説明会で総額を確認することが重要です。
参考文献・出典
- 文部科学省:「高等学校等就学支援金制度」
- 東京都教育庁(教育委員会):就学を支援する事業の御案内(奨学金制度)
- 東京都生活文化局:私立高等学校等授業料軽減助成金
- 通信制高校ナビ:通信制高校の学費・授業料はいくら?無償化(免除)方法も徹底解説
保護者としてできること・支援のポイント
高校選びだけでなく、保護者ができる支援・関わり方も整理しておきましょう。
子どもの気持ちを尊重する
ODの子どもは「自分だけこの病気で…」「普通の高校生活ができないかもしれない」という焦りや不安を抱えがちです。まずは「体がつらいのは甘えではない」「あなたのペースで進めばいい」というメッセージを、言葉・態度で伝えることが大切です。
学校との連携を早めに始める
- 志望校を検討し始めたら、学校説明会・個別相談会で「ODの場合どういう配慮があるか」「遅刻欠席が続いた場合はどう対応してくれるか」などを具体的に質問しましょう。
- 中学校の担任・保健教諭・医療機関とも情報共有をしておくと、進学後の“橋渡し”がスムーズになります。
体調管理・日常生活の環境を整える
- 高校生活は通学・授業・部活・行事と負荷が増えることもあるため、規則正しい生活リズム(起床・就寝・水分・塩分・下肢運動など)を継続できるよう、家庭環境を整えることが重要です。
セルフケアについては別記事で紹介しています。 - 通学前・授業前の調子を整えるために、登校前の光を浴びる、軽い運動をする、朝食をとるなどの習慣づくりが効果的とされています。
進学=ゴールではなく、次のステップと捉える
高校進学を“終わり”とせず、「学び・成長を続けるためのステップ」として捉えることが、ODの子どもが安心して選択をできる環境をつくります。
「どんな高校に行くか」ではなく「その高校で自分らして学び続けられるか」を一緒に考えることがポイントです。
説明会に参加する
全国各地で開催されている合同説明会に参加し、実際に高校の方から説明を聞くのも有効でしょう。
例:学びリンク「通信制高校・サポート校 合同相談会」
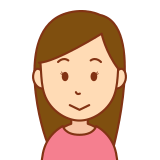
我が家の場合は、こちらに参加し、進学先の通信制高校を選択しました。
特徴ごとに学校が分布されている一覧表もあり、大変参考になりました。
まとめ:焦らず、自分(子ども)のペースを信じて選ぼう
ODを抱える中学生の高校選びでは、「普通の道」にこだわるより、「安心して通える道」を優先すること、つまり、「どんな高校に行くか」より、「その高校で自分らしく学び続けられるか」を重視する姿勢が何より大切です
全日制・定時制・通信制、それぞれにメリット・注意点があります。
体調・通学時間・学校の支援体制などを丁寧に確認しながら、子ども本人が「自分で選んだ」と感じられる高校を一緒に探してください。
学校が決まったら、その後は「通い続けられるかどうか」がカギです。
無理をして通学して体調が悪化してしまっては意味がありません。
日々の体調管理・家庭環境・学校との連携を意識しながら、子どもが自分のペースで学び・成長できる高校生活を描いていけるよう、保護者として温かく見守っていきましょう。
ご相談・カウンセリングのご案内
- 今の子どもの状態で、通える高校はある?
- どんな進路があるの?
- 選び方のポイントは?
このような思いを抱えておられる方もいらっしゃると思います。
そんな時は、ぜひご相談ください。
当事者家族として苦しんだ経験を持つカウンセラーが、あなたに寄り添い、進路決定への過程をサポートします。
「ひとりじゃないよ!」と寄り添っていきたいと思っています。
お気軽にご相談ください。




コメント