「起立性調節障害の子どもは、大人になったらどうなるのだろう?」
この問いは、ODを抱えるお子さんがいるご家庭から最も多く寄せられるものです。
朝起きられない、学校に通えない、体調が安定しない日が続くと、
「社会に出て働けるようになるのか」「症状は大人になっても続くのか」
と将来への不安が大きくなるのは自然なことです。
現に、起立性調節障害を抱える子の親として、私自身もこの悩みは現在進行形・・・
実際のところ、大人になるにつれて改善するケースが多い一方で、一定数では症状が長期化し、働き方・進学の選び方に工夫が必要なことも分かっています。
この記事では、
・大人になったときの症状の変化
・進路選びで気をつけたい点
・働き方の選択肢
・安心して社会に参加するための視点
を、最新の知見と実例をもとにやさしく整理します。
「この先どうなるの?」という不安を少しでも軽くし、お子さんの未来を描きやすくなるヒントをお伝えします。
起立性調節障害(OD)とともに大人になる――症状・変化を知ろう
大人になると症状はどう変化するのか
ODでは、思春期頃に発症することが多く、自律神経の調整不全により「朝起きられない」「立ちくらみがする」「体がだるい」などの症状を呈します。
例えば、あるレビューでは「大多数の軽症OD児は回復するが、重症群では長期的な不登校・睡眠障害・精神症状を伴うことがある」と報告されています。(参考:JMAjournal)
また、成人期の“起立不耐症/起立性調節障害(OI/OD)”を扱った実態調査では、3年以上症状が続き、歩行距離が1,000m未満となった「重症難治群」が22.2%を占めたという報告もあります。(参考:POTS and Dysautonomia Japan)
こうしたデータから言えるのは、
- 多くの場合、“時間をかけて改善”が期待できる
- ただし、一定数では症状が長期化・難治化しており、その場合は進路・働き方に配慮が必要
という二つの見通しを持つことが重要、ということです。
成人になったら完治・無症状になる、という確証はありませんが、「学び・働き方を柔軟に選ぶことで、自分らしく生きやすくなる」可能性は十分にあります。
働くこと・社会参加に向けての現実
成人の起立性調節障害・類似の自律神経不調(例えばPostural Orthostatic Tachycardia Syndrome:POTS)では、「立っているだけで通常の3倍のエネルギーを要する」「25%の人は働けない/障害手当を申請している」という報告があります。(参考:Employment and POTS)
また、米国のクリーブランド・クリニックによるPOTSの予後報告では「約80%の症例で改善傾向にあるが、残存症状を抱える人も多く、日常生活・就労に影響あり」 とされています。(参考:Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome (POTS))
このような背景から、
- OD/起立不耐症を抱えたまま「働く」ことを考えるなら、働き方・勤務形態・職場環境・休憩の取り方などをあらかじめ準備する
- 安定通勤・フルタイム勤務・立ち仕事といった“普通”の働き方が難しいケースもあるため、選択肢を広く持つこと
- 症状の波を見越して、「働ける時期」「休みが必要な時期」を自分・家族・職場で共有できるようにする
という視点が不可欠です。
起立性調節障害(OD)の子の進路選び・就職活動で知っておきたいポイント
学び/専門学校/大学で気をつけること
ODの後、「高校を卒業したら大学・専門学校」という選択をする子どももいます。そうした際、次の点を確認しておくと安心です:
- 出席要件・休学制度・サポートセンターの有無:症状が不安定なときには、オンライン授業・レポート提出・休学が可能な制度があるかを事前にチェック
- 自宅通学が可能な学校を選ぶ:体調の波がある場合、通学距離・通学方法・通学時間が大きな負荷になります
- 学習時間を自分で調整できるコース:通信制・夜間コース・単位制など、無理をせずに“自分のペース”で学べる選択肢を検討
こうした準備があれば、ODを抱えながらでも「学び続ける」「進学する」という選択肢を閉ざす必要はありません。
参考:高校進学の不安がある方へ
「高校選びで迷っている」「通信制と全日制の違いが分からない」
そんな保護者の方向けに、こちらで詳しく整理しています。
働き方/就職先選びのヒント
働き始める際には、以下の観点をぜひ押さえておきましょう。
- 勤務形態の柔軟性:時短勤務・在宅勤務・変則勤務・フレックス勤務など、体調に応じた働き方を許容してくれる職場を探す
- 仕事内容・勤務時間・通勤条件の検討:長時間立ち仕事・通勤ラッシュ・重い荷物を扱う職場は症状を悪化させる可能性あり
- 自己理解と説明力:「自分は立ちくらみ・倦怠感が出やすい」「通勤時間・休憩時間をこうしたら調子が保てる」ということを自分で把握し、職場・上司に説明できるように準備する
- 障害者雇用・特例子会社も選択肢に:OD/起立不耐症のような自律神経の乱れを伴うケースでは、障害者雇用枠・配慮ある職場を選ぶメリットがある
- 体調変化時のバックアップ・休息の確保:症状が悪化したときに、休職・時短・部署変更などの制度が整っているかも確認する
こうした準備を整えておけば、「ODを抱えていても働けないのでは?」という不安を少しずつ和らげ、自分らしい働き方を選びやすくなります。
体調管理と職場でのスタンス
- 毎日の生活リズムを整えておく(起床・就寝・水分補給・塩分・適度な運動)
- 通勤・勤務中の体調サインを無視せず、早めに対策(椅子に座る、足を上げる、飲水など)
- 職場に「体調の変化が出やすい」ことを理解してもらい、無理せず「休む勇気」を持つ
- 「症状があっても価値ある働き手である」ことを自分自身も職場も確認できるよう、成果や強み・得意な働き方を把握しておく
職場の理解を得たとしても、自己の安定性を継続し続けることは大切なことです。
参考:家でできるセルフケアを知りたい方へ
「具体的な方法がわからない」「ポイントは何?」
そのような疑問をお持ちの方向けに、こちらで5つの習慣についてにまとめています。
回復・改善に向けて持っておきたい視点
時間をかけての改善が期待できる
ODを含む起立不耐症・自律神経不調では、“短期間で完治”とまでは言えないものの、長期的に改善する見込みが高いという報告があります。
例えば「POTSでは約80%が時間とともに改善傾向にある」とされています。(参考:Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome (POTS))
別の観点では、小児ODの研究レビューでも、「軽症例では回復するものが多数」と示唆されています。(参考:JMAjournal)
このように「時間をかけて少しずつ回復を目指す」という姿勢が大切です。
残る症状・波のある日々を理解しておく
ただし、改善しても「体調の波(調子が良い日/悪い日)」が続くという実態もあります。OD類似POTSの実態調査では、症状が3年以上続き1000m未満の歩行距離となった「重症難治群」も22.2%存在しています。(参考:POTS and Dysautonomia Japan)
このことから、「100%無症状になる」と予想しすぎず、「ある程度の配慮が必要な時期があって当然」と認識しておくことが、本人・保護者・職場にとって安心材料となります。
自分らしい暮らし・働き方をデザインする
改善を目指すうえで、「治す」ことだけでなく「調子を整えながら暮らす・働く」視点も重要です。「自分らしい生き方」をテーマに据えるなら、次のような視点を持つと良いでしょう。
- 自分の体調の“リズム”を把握する:朝/午後/夕方にどの程度調子が出るか、どんな負荷で症状が出やすいか
- 仕事・学び・生活を「無理しない範囲」で選ぶ:例えば「通勤時間を短くする」「座ってできる仕事を選ぶ」「在宅勤務を検討する」
- 周囲と連携する:家族・職場・学校・医療機関・支援団体をつなぐネットワークを持つ
- 体調が崩れたときの“リハビリ・休息プラン”を持つ:無理をして症状が悪化すると回復に時間がかかるため、早めに休む・ペースを緩める工夫を
働き方/生き方を考えていくことを「キャリアデザイン」と言います。
ODを抱えていても、その人に合ったキャリアは必ず作れます。
そのために必要なのは「ひとりで抱え込まないこと」です。
ご自身やご家族で考えていくのは難しいなと思われる場合は、キャリアコンサルタントなどの専門家に相談するのもよいでしょう。ODやその他生きづらさを抱える方の支援が経験豊富な方だと、なお心強く感じることと思います。
まとめ:起立性調節障害(OD)を抱えても、進学/就労の可能性は広がる
ODという診断を受けると、「将来どうなるのか」「働けるのか」「普通の暮らしができるのか」という不安を抱えるのは当然です。しかし、症状の改善が見られるケースが多数あり、また、働き方・学び方を工夫することで「自分らしく生きる」道は確実にあります。
重要なのは、次の3つです:
- 症状の波・個人差を理解し、「無理をしないペース」を大切にする。
- 学び・働きの選択肢を幅広く持ち、自分に合った環境を選ぶ。
- 周囲と連携し、支援を受けながら「自分のペース」で次のステップへ進む。
ODを抱えた子どもたちが、将来「自分で選び・自分で働き・自分らしく生きる」ために、この記事が少しでも力になれば幸いです。
ご相談・カウンセリングのご案内
- 自分にとって無理をしなペースって何?
- 働き方の選択肢が思いつかない
- 自分にあった環境とは?
- 利用できる支援にはどんなものがある?
- どう動いていいのかわからず、ただただ不安ばかりが襲ってくる…
このような声をご相談で多く伺います。
体調・進路・将来について一人で抱えこまなくて大丈夫です。ぜひご相談ください。
- 体調の波をふまえた“現実的な選択肢”の整理
- 学校・専門学校・会社への説明文の作成サポート
- 子どもと保護者の間の“認識のすり合わせ”
- 進路相談・就職相談・日常生活のリズムづくり
ひきこもりや身心不調など生きづらさ働きづらさを抱える方の就労支援に携わっており、また、当事者家族として現在進行形で悩み続けているカウンセラーが、あなたに寄り添い、「自分らしく働く」「自分らしく生きる」を叶えていきます。
ご希望の方は下記からご予約ください。
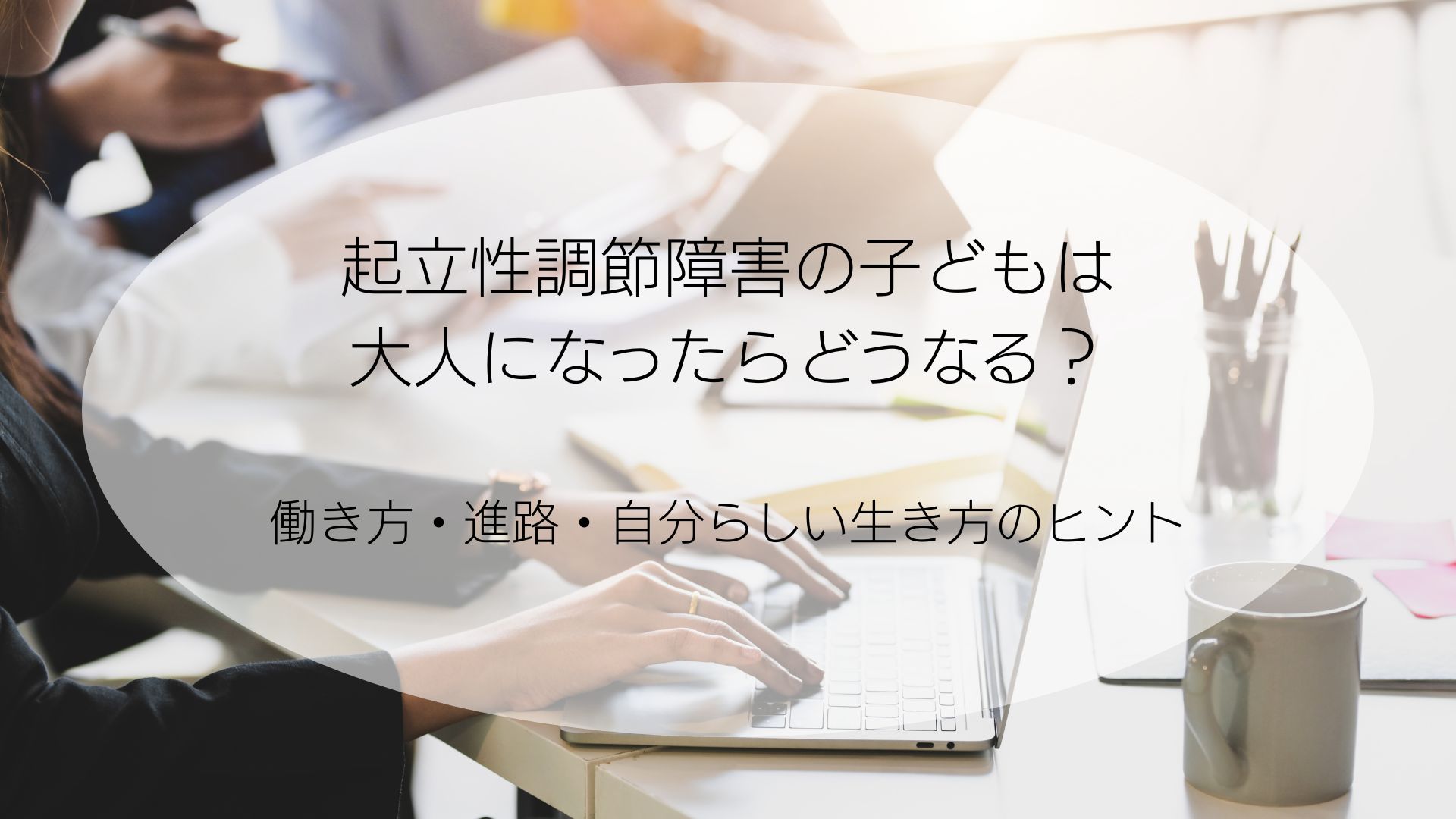




コメント