朝起きられない子どもたちが増えている?
「朝になると体が重くて動けない」「起こしても布団から出られない」――。
そんな子どもの様子に戸惑い、不安を感じる保護者の方は少なくありません。
実はその背景には、「起立性調節障害(OD)」という、自律神経の不調が隠れていることがあります。
この症状は以前から存在していましたが、近年、発症する子どもが明らかに増えていることが、複数の医療機関や教育機関から報告されています。
なぜ今、起立性調節障害の子どもが増えているのでしょうか?
この記事では、現代の子どもたちを取り巻く環境や背景を探りながら、大人にできる支え方を紹介します。
起立性調節障害とは?
起立性調節障害(Orthostatic Dysregulation/OD)は、自律神経のバランスが乱れることにより、立ち上がったときに血圧や心拍数がうまく調整できなくなる疾患です。
主な症状には次のようなものがあります:
- 朝、起き上がれない
- めまい・立ちくらみ
- 動悸・息切れ
- 倦怠感・頭痛
- 午前中に不調が強く、午後からは少し元気になる
見た目ではわかりにくいため、「怠けている」「サボっている」と誤解されやすいのが、この病気のつらいところです。
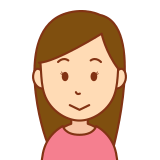
当事者の親である私も、初めは「なぜ?」と思い、状況が続くと「怠けてる」「サボり癖?」などと思ってしまいました。
今から思うと、その気持ちが子どもを追い込んでいたのですね。
起立性調節障害が増えている背景とは?
自律神経に負荷をかける現代の生活環境
スマートフォンやタブレットなどのデジタル機器は、子どもたちにとっても身近な存在になりました。
しかし、ブルーライトや長時間の画面視聴は、交感神経を刺激し、睡眠の質や体内時計に悪影響を与えます。
また、遊びや自然とのふれあいの時間が減り、「身体を使う・休む・眠る」という基本的なリズムが乱れがちになっています。
学校・家庭でのストレスの増加
- 成績や進路へのプレッシャー
- 学校での人間関係やいじめ
- 家庭内の不和や過干渉・無関心
こうしたストレスが積み重なると、自律神経は常に緊張モードになり、うまく切り替えができなくなります。
精神的なストレスが強い場合は、「身体症状として表れる」こともあります。これは決して珍しいことではありません。
オンライン化と夜型生活
コロナ禍以降、オンライン授業・オンラインゲーム・SNSの使用時間が増加。
子どもたちの生活は夜型化し、「昼夜逆転」になってしまうケースも多く見られます。
特に、深夜までゲームやYouTubeを見ている子どもは、交感神経が休まらず、眠りの質が低下してしまいます。
コロナ禍による生活リズムの崩壊
- 臨時休校や分散登校で「朝起きる必要」がなくなった
- 家で過ごす時間が増え、昼夜の境目がなくなった
- 運動不足で体力が低下し、自律神経が弱まった
これらが、OD発症や悪化の引き金になったと考えられています。
医療現場では、「コロナ以降にODの相談が急増した」という声が多数上がっています。
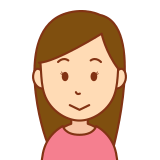
実際に我が子も、起立性調節障害(OD)を発症したのは、コロナ禍に行われた3か月間の休校がきっかけでした。
生活リズムや対面からオンライン授業への変更等、環境の変化が大きなストレスとなったのでしょう。
「見逃されやすい」子どもたちのサイン
起立性調節障害の子どもは、午後になると元気そうに見えることがあります。
そのため、「朝は仮病なのでは?」と疑われたり、「午後から登校できるなら大丈夫でしょ」と判断されたりしてしまいます。
でも、実際には…
- 起き上がると心拍数が急に上がる
- 頭がボーッとして集中できない
- 無理して登校すると、次の日さらに悪化する
など、身体の中で激しい負荷がかかっている状態なのです。
子どもの「なんとなく元気がない」「起きてこられない」「登校しぶりが続く」といった変化は、大人が見逃さず、丁寧に拾い上げる必要があります。
家庭・学校・社会ができる支え方
医療機関での診断と治療
まずは小児科や心療内科で正確な診断を受けることが大切です。
診断がつくことで、周囲も適切な対応がしやすくなりますし、学校との相談もスムーズに進めやすくなります。
家庭での支え方
- 朝のルーティンを一緒に整える(朝日・ぬるめのシャワーなど)
- 「頑張れ」ではなく「今は休んでいいよ」と伝える
- 元気なときだけでなく、調子が悪い日にも関わる
- 食事や睡眠をサポートする
親が焦る気持ちはよくわかりますが、叱るよりも寄り添う姿勢が、子どもにとっての「安心安全の基地」になります。
学校での調整や配慮
- 午前中は自宅で過ごし、午後だけ登校する「分割登校」
- 保健室登校、放課後登校、フリースクールとの併用
- 出席扱いにするための医師意見書提出
柔軟な対応が、子どもの自己肯定感を保つことにもつながります。
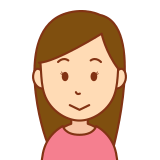
私の場合は、まず、公的な教育機関で相談しました。そこで「起立性調節障害かも」と教えていただき、通院するに至りました。
病院では、学校生活が負担にならないようにと、医師が意見書を書いてくださいました。
私は学校に、起立性調節障害に関する書籍を寄贈し、先生やクラスメイトに理解を求めました。
親にできることは少ないですが、できることはやっていきたいと思い行動しました。
増えているからこそ、「怠け」と決めつけない視点を
近年のODの増加は、決して「弱い子どもが増えた」わけではありません。
社会全体がストレスフルになりすぎているのです。
- 大人が「これは病気かもしれない」と理解すること
- 「甘え」と切り捨てず、「支援の対象」として捉えること
それだけで、子どもは「否定されなかった」と安心し、前に進む力を取り戻すことができます。
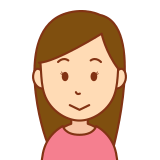
まず、親が理解する。そして、周辺に理解を広げていく・・・この行動が親ができることであり、親しかできないことだと思います。
「理解する、そして、現状を受け入れる」
ここが何より難しくてしんどい過程だと思います。
まとめ
【図表】起立性調節障害(OD)増加の背景と対策まとめ
| 背景要因 | 具体例 | 主な影響 | 推奨される対策 |
|---|---|---|---|
| 生活習慣の乱れ | 夜型生活、スマホ長時間使用、睡眠不足 | 自律神経の昼夜リズムが乱れる | 睡眠・起床時間の見直し、就寝前のデジタルデトックス |
| 心理的ストレス | 学校不適応、いじめ、家庭不和、不安 | ストレスによる交感神経過活性・副交感神経の機能低下 | スクールカウンセラー利用、心理的支援、安心できる環境づくり |
| コロナ禍による影響 | オンライン授業、外出制限、運動不足 | 身体機能の低下(デコンディショニング)、体内時計の乱れ | 運動療法、段階的登校支援、外出や社会参加の機会確保 |
| 身体的要因 | 発育期のホルモン変化、自律神経未熟 | 血圧調整や脳血流のコントロールが不安定 | 医療機関による新起立試験・診断、適切な薬物治療や生活指導 |
| 社会的誤解 | 「怠け」「甘え」とみなされる | 本人・家族が孤立、支援の遅れ | ODの正しい知識の啓発、教職員や保護者への研修 |
起立性調節障害が増えているのは、子どもたちの身体や心に、現代社会のさまざまな負荷がかかっている証拠です。
「怠け」ではなく、「体の声」として受け止め、医療・家庭・学校が連携して支えていくことが何より大切です。
今、不調の渦中にいる子どもも、適切な支援によって、少しずつ元気を取り戻すことができます。
ご相談・カウンセリングのご案内
「うちの子、もしかして起立性調節障害かも?」
「毎朝、起こすだけで親子ともに疲弊している」
そんなときは、一人で抱え込まずにご相談ください。
当相談室では、
- 起立性調節障害のお子さんへの関わり方
- 学校や支援機関との連携サポート
- 保護者の気持ちの整理やストレス対処
などを専門的にサポートしています。
お気軽にご相談ください。
▼参考 日本小児科学会:ガイドライン(PDF)
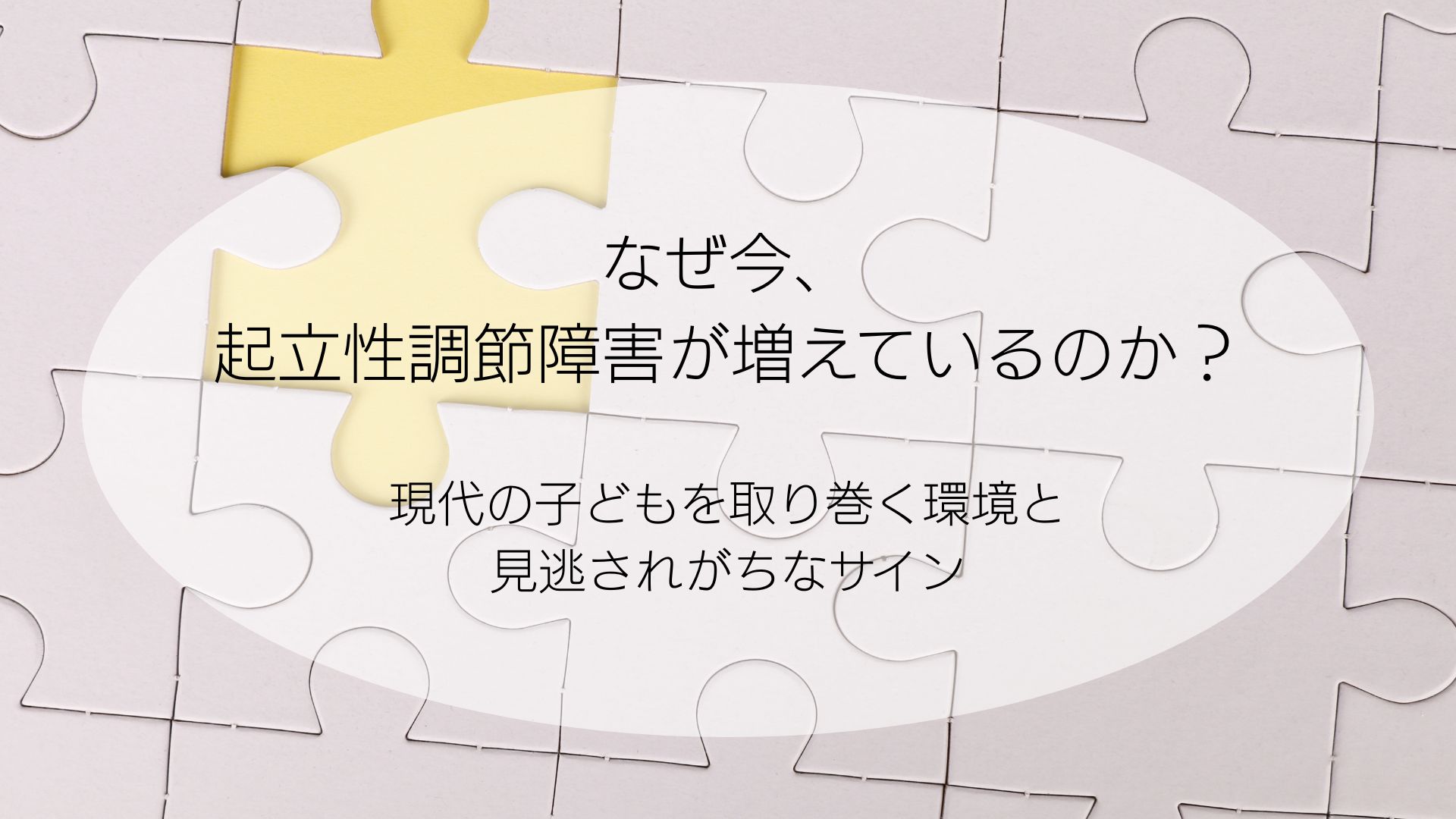


コメント