起立性調節障害とは?──まずは基本から
「朝になると頭が痛い」「体がだるくて学校に行けない」「午後には元気なのに」
そんな思春期の子どもを見て、「本当に病気なの?」「怠けてるのでは?」と戸惑った経験はありませんか?
それはもしかすると、「起立性調節障害(Orthostatic Dysregulation/OD)」かもしれません。
この病気は、思春期の子どもに多く見られる自律神経の不調で、朝に特有の症状が強く出るのが特徴です。
けれどその特徴ゆえに、周囲の理解が得られにくく、「甘え」「サボり」と誤解されがち。
この記事では、起立性調節障害に関するよくある質問10個に丁寧にお答えしながら、正しい理解と適切なサポート方法について解説していきます。
Q1:起立性調節障害って本当に病気なの?「甘え」じゃないの?
A:はい、れっきとした身体の病気です。
起立性調節障害は、自律神経がうまく働かず、体を起こすと血圧や心拍数の調整が乱れる状態です。
その結果、脳への血流が足りずに「めまい」「立ちくらみ」「倦怠感」などの症状が出ます。
午後には自律神経の働きが安定し、症状が軽減するため、元気に見える時間があるのもこの病気の特徴です。
つまり「午前はしんどいのに午後は元気」=「サボってる」ではなく、「そういう病気の症状」なのです。
Q2:どんな症状があるの?朝だけ?
A:午前中を中心に、以下のような症状が見られます。
• 朝起きられない(頭痛・だるさ・吐き気)
• 立ちくらみ・めまい・動悸
• 食欲不振・朝に食べられない
• 午前は寝たきりでも、午後は活動できる
• お風呂でののぼせや、外出時の体調不良
これらの症状は、日によって強さが変わるのも特徴です。体調の波があることも理解しておきましょう。
Q3:なんで朝だけ?午後になると元気になるのはなぜ?
A:朝は交感神経がまだうまく働いておらず、体が「活動モード」に入っていないからです。
体が目覚めるには、血圧を上げ、心拍を整え、血液を全身に巡らせる必要があります。
起立性調節障害の子はこの調整がうまくいかず、脳への血流不足で動けなくなるのです。
午後になると自律神経の働きが安定し、体調が回復することが多いため、午後だけ元気に見えるのはむしろ典型的なパターンです。
Q4:何歳くらいに多い?大人になったら治るの?
A:主に小学校高学年~中学生の思春期に多く見られます。
発症年齢のピークは10~16歳ごろ。
統計では、小学生で約5%、中学生では約10%が起立性調節障害の傾向を示すとされています。
体の成長とともに症状は自然に落ち着くケースも多く、約8~9割が数年以内に回復すると言われています。
ただし、放置すると不登校や生活リズムの乱れが慢性化するリスクもあるため、早期対応が望まれます。
Q5:原因は何?生活習慣のせい?
A:原因はさまざまですが、以下の要因が重なって発症することが多いです。
• 自律神経の感受性(体質)
• 思春期のホルモン変化や急激な成長
• 夜更かし・睡眠不足・スマホの長時間使用
• 精神的ストレス(学校・家庭など)
「ただの生活習慣の乱れ」と切り捨てず、環境や心理的な要因にも目を向けることが大切です。
Q6:何科を受診すればいい?検査は痛いの?
A:まずは小児科・内科を受診し、「思春期外来」や「自律神経外来」への紹介を受けるのが一般的です。
主な検査には、
• 起立試験(横になってから立ち上がり、脈拍や血圧の変化を確認)
• 問診と生活状況のヒアリング
• 血液検査(貧血などの除外)
などがあり、特別な痛みを伴う検査はほとんどありません。
Q7:治療法は?どれくらいで治るの?
A:治療の基本は「生活改善」と「環境調整」です。
主な対策:
• 規則正しい生活リズム(夜更かしNG)
• 朝起きたら布団の中で体を動かす
• 水分・塩分補給(経口補水液やみそ汁など)
• 太陽の光を浴びる
• 軽い筋トレやストレッチ
• 加圧ソックスの使用
症状の程度によっては、医師の判断で昇圧剤や漢方薬などの処方が行われることもあります。
回復には数ヶ月~数年かかることもありますが、適切な対応で多くは改善が見込めます。
Q8:親や学校ができるサポートって何?
A:理解と環境調整が何よりの支えになります。
家庭でできること
• 「甘え」ではなく「病気」であると理解する
• 起床補助(声かけ・明るくする・保温)
• 朝の水分・塩分補給の習慣づけ
• 「登校ありき」で責めず、体調を見ながら判断
学校にお願いできること
• 保健室登校の許可
• 午前中の授業配慮(遅刻・別室対応など)
• 出席扱いの配慮(医師の診断書を活用)
無理をさせると逆効果になることもあるため、体調に応じた柔軟な対応が重要です。
Q9:遊びに行けるのに学校に行けないって、本当?
A:本当です。それがまさに起立性調節障害の特徴です。
午後になると体調が良くなり、好きなことやストレスの少ないことには対応できる状態になることがあります。
しかし学校には「集団」「緊張」「責任感」「朝早くから動く」といったハードルがあるため、本人の中で「行きたいけど体がついていかない」状態に。
一見すると「都合よく動いているように見える」かもしれませんが、本人にとっては必死の調整の結果なのです。
Q10:放っておいても大丈夫?自然に治るって本当?
A:自然に治るケースもありますが、放置はリスクを伴います。
適切な対応をしないまま不登校が続いたり、生活リズムが崩れたまま大人になると、以下のような二次的な問題が生じることもあります。
• 生活習慣病・うつ状態・引きこもり
• 学校や社会への復帰が難しくなる
• 自尊感情の低下
早期に気づき、専門機関やサポートを利用することで、よりスムーズな回復が期待できます。
まとめ:まずは「知ること」がはじめの一歩
起立性調節障害は、「本人にも原因がわからず、苦しんでいる」ことの多い病気です。
本人のつらさに寄り添いながら、少しずつ生活と心のバランスを整えるサポートが求められます。
個別のご相談も受付中です
「学校に行けないことをどう受け止めればいいかわからない」
「病院には行ったけど、生活のサポートまではしてもらえなかった」
「親としてどう対応すればいいの?」
そんな時は、一人で抱え込まずに、専門家と話してみませんか?
当相談室では、起立性調節障害をはじめとする個別相談を受け付けています。
オンラインで全国対応・初回相談無料のメニューもございます。
▶︎ 当相談室の詳細を見る
▶︎ お問い合わせはこちらから
▼起立性調節障害についてこちらにもまとめています
執筆にあたり参考にしたリンク
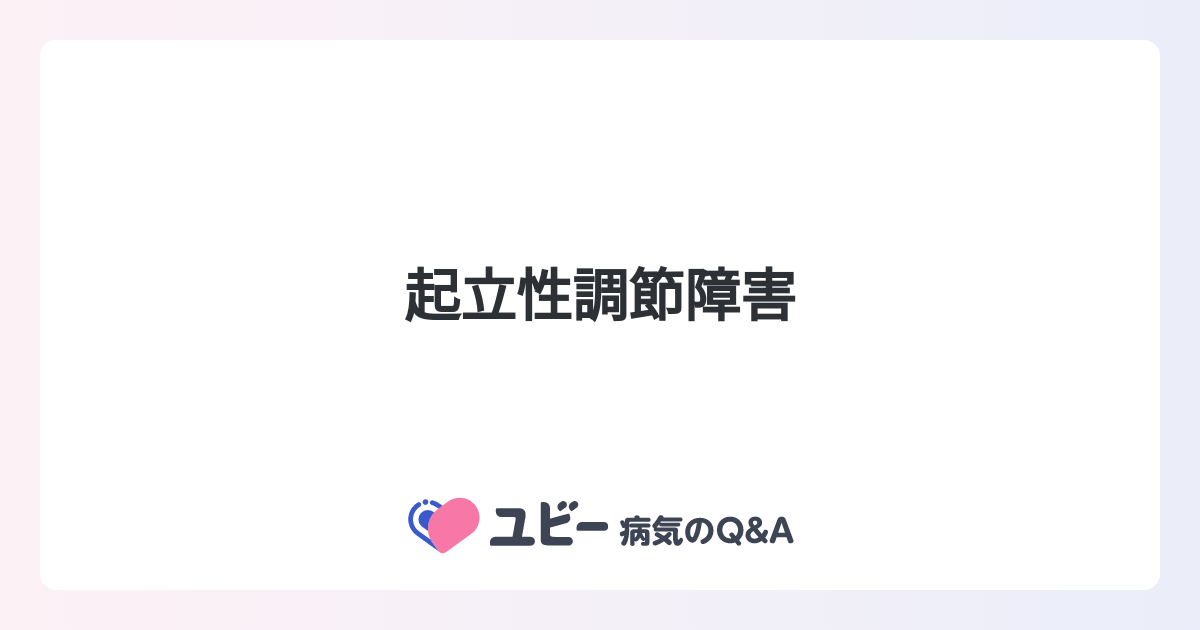


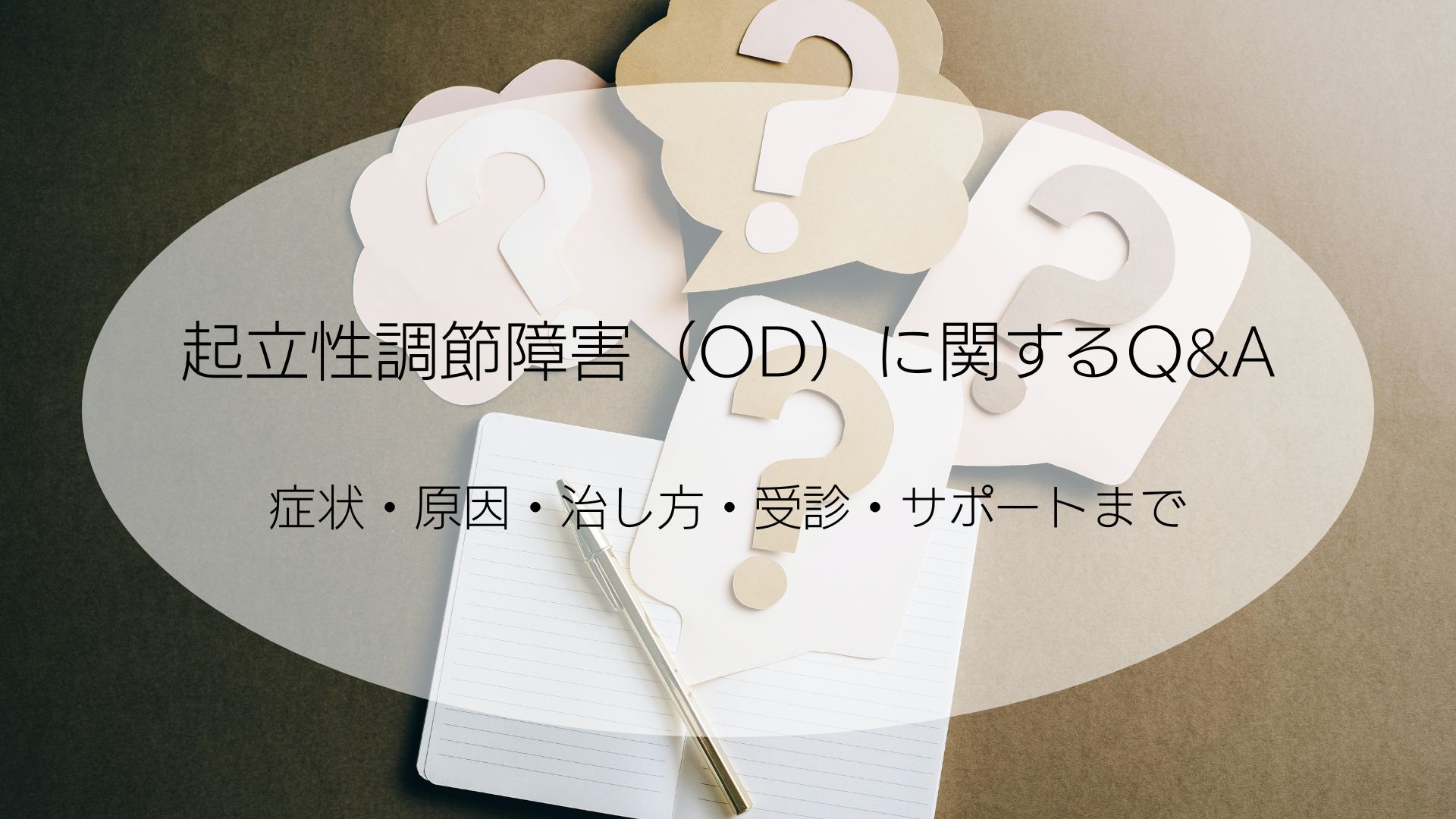
とは?-朝起きられないのは「怠け」じゃない_アイキャッチ-160x90.jpg)

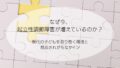
コメント