「朝になると、頭が痛い」「身体が重くて動けない」――
そんな症状に悩む子どもが、少しずつ増えています。
学校に行けない、でもそれを「怠け」「甘え」と受け取られてしまう。
その背景には、「起立性調節障害(OD)」という身体の病気が隠れていることもあります。
2024年6月、朝日新聞の連載『患者を生きる』では、起立性調節障害を抱える子どもとその家族の体験が、紙面にて6回、webサイトでは2回にわたって紹介されました。
症状の深刻さと回復までの道のりが、実例を通してリアルに描かれています。
「学校に行けない」は、怠けではない――症例から見える不調の始まり
最初に現れたのは、頭痛と微熱。学校を休むことが増えたのは、小学校3年生の終わりでした。
近所の病院を受診しても「異常なし」。それでも、子どもは苦しんでいる――。
保護者も「これでいいのか」と迷い続けます。
ようやくたどりついたのが、「起立性調節障害」という診断でした。
自分の気持ちを伝えられるようになるまでの、長い道のり
記事の中では、食欲不振が続いて痩せすぎ、筋力低下でトイレに行くことも難しくなった時期の話が紹介されていました。
一時は、ほぼ寝たきりの状態になり入院していた子が、何年かして「どうしたいか」「何がつらいか」等自分の言葉で説明するようになっていく。
こうしたプロセスは、「ただ体調が戻る」だけでなく、その子自身の成長と回復の物語でもあります。
医師の言葉でわかる起立性調節障害の本質:「これは身体の病気です」
連載には、専門医の言葉も掲載されています。
自律神経の乱れにより、立ち上がったときに脳への血流が下がることが原因
この病気は完治を目指すのではなく、自分なりに症状と折り合いをつけながら日常生活を送ることができれば、一歩前進
これらの言葉は、当事者や家族にとって、大きな支えになることでしょう。
体調に波があり、外からは見えにくい病気だからこそ、「病名と専門家の理解」が周囲との信頼関係の鍵になります。
▼こちらで「起立性調節障害」について詳しく説明しています。
当事者が「わたしも同じだった」と思えるOD症例の紹介
紹介されている方のエピソードは、今この記事をお読みの方が体験してきたことと異なる場合もあるでしょう。
でも、共通しているのは――
- 症状が「わかってもらえない」苦しさ
- 親も本人も「これでいいのか」と迷う日々
- 小さな変化に希望を見出していく姿
「まさにうちの子と同じだった」「自分もそうだった」と思う方も多いのではないでしょうか。
記事リンク(朝日新聞デジタル・一部無料)
以下のリンクから、新聞記事の一部を読むことができます(※全文は有料会員登録が必要です)。
• 朝起きられない娘「学校に通わせないと」 母の呪縛をほどいた一言
• 病と闘う17歳、怠けてないのに「悔しい」 娘の成長、気づいた父は
• 起立性調節障害、中学生の10人に1人が発症 求められる親の覚悟
ご家族の不安が、少しでも軽くなるように
「学校に行けない子どもに、どう接すればいいのか」
「このまま進学・就職できるのか不安」
そんな悩みを抱える保護者の方は少なくありません。
起立性調節障害は、見えにくく、周囲の理解が得られにくい病気です。
だからこそ、情報とつながりが必要です。
起立性調節障害に関するご相談・カウンセリングはこちら
当相談室では、起立性調節障害のお子さんやご家族のための個別カウンセリングを行っています。
-
症状が続いていて不安な方
-
学校・家庭での対応に悩む方
-
将来をどう考えてよいかわからない方
どんな小さなことでもかまいません。まずはお話をお聞かせください。
お話を伺いながら、一緒に希望を見出していけたらと思っています。
▶︎ [個別カウンセリングの詳細はこちらへ]
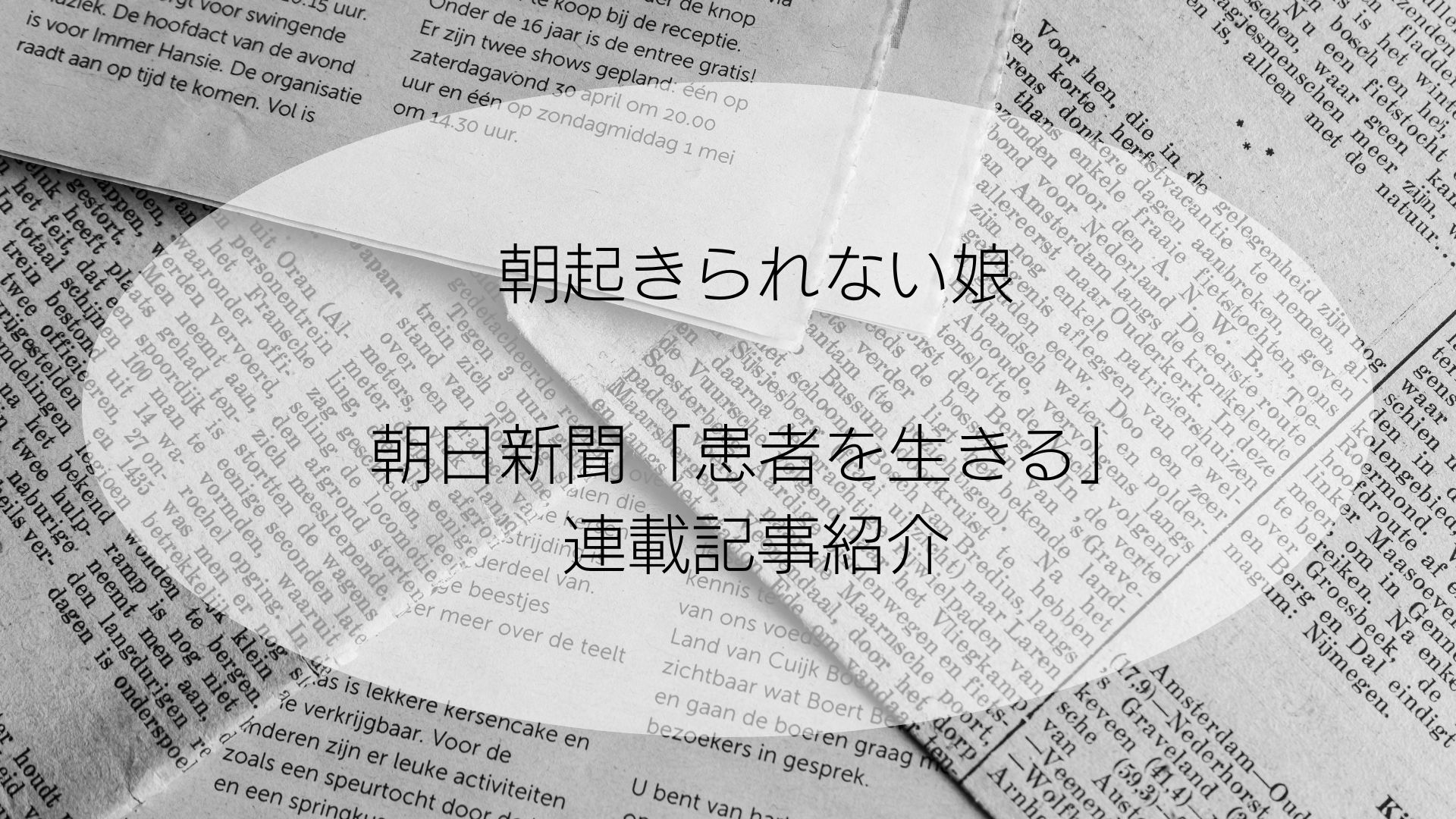
とは?-朝起きられないのは「怠け」じゃない_アイキャッチ-160x90.jpg)

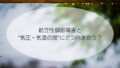
コメント