「ただの怠け」「夜更かしのせい」——。もし、あなたのお子さんが毎朝起きられず、学校に行きたくても行けない状況に苦しんでいるなら、それは起立性調節障害(OD)かもしれません。さらに、ODの症状を抱える子どもの中には、発達障害(DD)の特性が併存しているケースが少なくありません。
この複合的な困難は、一般的な不登校の支援だけでは解決が難しく、子どもたちを深く追い詰めています。
本記事では、この二つの問題がなぜ重なり、子どもたちの生活にどのような影響を与えているのかを、現在の事象とデータから明らかにします。この見過ごされがちな実態を理解することが、お子さんへの正しい支えの第一歩と考えています。
データが示す事実:なぜODとDDは併発しやすいのか
近年、起立性調節障害(OD)に関する情報や理解は深まりつつありますが、その背後に発達障害(DD)の特性が潜んでいるケースがあることは、まだまだ知られていません。
ODは「自律神経の不調」、DDは「脳機能の特性」
まず、それぞれの基本的な「事象」を確認しましょう。
- 起立性調節障害(OD):成長期の子どもに多く見られる、自律神経の働きの不調です。起立時に重力の影響で足元に溜まった血液を心臓や脳へ戻す指令が上手くいかず、脳の血流が低下することで、朝起きられない、立ちくらみ、頭痛、倦怠感などの症状を引き起こします。午後には症状が軽くなるのが特徴です。
下記記事で詳しく説明していますので、ぜひ参考にしてください。
- 発達障害(DD):生まれつきの脳機能の特性によって、日常生活や社会生活に困難が生じる状態です。代表的なものに、ASD(自閉スペクトラム症)やADHD(注意欠如多動症)などがあります。
1-2. 複数の調査で示される「高い併存率」
この二つの事象は、実は高い確率で重なり合っています。
ある小児循環器学会の報告や、小児科の臨床研究の結果によると、起立性調節障害と診断された子どものうち、10%〜30%以上で発達障害の特性が併存していることが示されています。特定のクリニックでのフォローアップ例では、ODの子どもの約4割がASDやADHD、不安抑うつ状態などの診断を受けていたというデータもあります。
【根拠となる情報源】
- 日本小児循環器学会報告:OD児の20~30%に発達障害の合併があるとされる([II-OR20-05] 起立性調節障害と発達障害)。
- 臨床研究データ:起立性調節障害132例中、18例(14%)で発達障害が併存(犬塚, 日児誌 119, 977-984, 2015)。
ODの症状だけに着目していては、背景にあるDDの特性を見逃してしまう可能性があるのです。
見過ごされがちな構造:発達特性が引き起こす「自律神経の乱れ」への負荷
なぜ、脳機能の特性である発達障害が、身体の不調である自律神経の乱れにまで影響を及ぼすのでしょうか。そのカギは「ストレス」と「環境への適応」にあります。
2-1. 日常生活で特性が「過度なストレス」に変換される
発達障害の特性を持つ子どもたちは、周囲が気づきにくいところで、健常児以上の精神的・身体的な負荷に晒されている可能性があります。
- 感覚特性によるストレス: ASDなどでは、教室の騒音、給食のにおい、制服の肌触りなど、多くの人が気にしない感覚的な刺激が、子どもにとっては耐えがたいストレス源となります。
- 社会性・コミュニケーションの困難: 集団生活の中で「空気を読む」「暗黙のルールを理解する」といった行動が苦手なため、常に緊張状態にあり、知らず知らずのうちに大きな疲労を蓄積します。
- 衝動性・多動性による疲労: ADHDの特性により、授業中座っていることが苦痛であったり、衝動的な行動をしてしまうことで自己嫌悪に陥ったりします。常に脳がフル回転している状態は、身体的疲労の回復を妨げます。
2-2. ストレスの蓄積が自律神経を疲弊させるメカニズム
これらの「過度なストレス」は、最終的に自律神経の乱れという形で身体に現れます。
自律神経は、ストレスから身体を守るために交感神経(緊張・活動モード)を優位にしますが、DDの特性によってストレスが慢性的に続くと、交感神経が過剰に働き続けて疲弊します。
特に、体内時計の乱れも併発しやすいことが知られており、不規則な睡眠や覚醒を繰り返すことで、身体はさらに疲弊します。この精神的ストレスと身体的ストレスの悪循環が、起立性調節障害の症状である「朝起きられない」「立ちくらみ」などを悪化させる要因となっているのです。
【根拠となる情報源】
- 発達障害の特性を持つ子どもは通常の環境でもストレスが過度にかかり、そのストレスが自律神経の乱れへと繋がってしまう([OD/DDに関する情報提供サイト])。
子どもの生活に広がる影響:朝起きられないことから始まる不登校という大きな壁
ODとDDの複合的な困難は、子どもの学校生活に決定的な影響を与えます。最も顕著なのが不登校という事態です。
3-1. 不登校の子どもの約3割〜4割にODが併存
朝起きられないというODの主症状は、遅刻や欠席を繰り返すことにつながります。そして、欠席が長期化することで不登校の状態に移行するケースが非常に多いのが現状です。
データとしても、不登校になっている児童生徒の約30%〜40%に起立性調節障害が併存していることが示されています。
【根拠となる情報源】
- 不登校の30~40%にODが併存する([日本大学医学部附属板橋病院]、[ツナグバ])。
ODという身体の病気が、不登校の主要な原因の一つとなっていることは、もはや看過できません。
3-2. 誤解と自己否定の悪循環
さらに、ODとDDが併存する場合、子どもたちはより複雑な苦しみを抱えます。
- 身体の不調(OD): 朝起きられない、体がだるい、頭が痛いといった症状で、学校に行きたくても行けない。
- 周囲の誤解: 周囲からは「やる気がない」「わがまま」「夜更かししている」と誤解され、叱責を受ける。
- 発達特性による困難(DD): 学校での人間関係や学習に元々困難を抱えており、登校できなくても安息が得られない。
- 自己肯定感の低下: 朝起きられない自分、皆と同じようにできない自分を責め、「自分はダメな人間だ」という感覚が強まる。
このように、複合的な困難は、子どもが自分自身を肯定する力を奪い、引きこもりなど次の段階の困難へ移行するリスクを高めてしまうのです。
必要なのは「二つの困難」への同時アプローチ:特性を考慮した支援の重要性
このODとDDが重なる複雑なケースにおいては、ODの身体症状だけを改善しようとしても、根本的なストレス源(発達特性への不適応)が残っているため、症状が改善しにくいことが指摘されています。
4-1. 「基本的治療だけでは改善が乏しい」という専門家の見解
小児循環器学会の報告でも、ODへの一般的な治療(薬物療法や生活指導)のみでは症状改善が乏しく、発達障害特性を考慮した介入が症状改善に役立つという事例が紹介されています。
【根拠となる情報源】
- 小児循環器学会報告(再掲):ODへの基本的治療のみでは症状改善が乏しい([II-OR20-05])。
専門家は、ODの治療と同時に、発達特性をアセスメントし、学校や両親へ適切な情報提供を行うことが有効であると強調しています。
このことは、加藤善一郎著『マンガ 脱・不登校』をはじめとする、各種書籍にも記載されています。
起立性調節障害に関する書籍を、下記で詳しく説明しています。よろしければお読みください。
4-2. 特性を理解した具体的な「環境調整」
では、具体的にどのような「特性を考慮した支援」が必要なのでしょうか。
- 学校での合理的配慮: 登校時間を遅らせる(午後登校の許可)といったODへの配慮に加え、DD特性への環境調整が不可欠です。例として、騒音が苦手な子には座席を窓際から離す、視覚的な情報処理が苦手な子には板書を写真に撮ることを許可するなどです。
- 家庭でのストレス軽減:
- 感覚過敏を刺激するような環境を排除する(特定の衣類を避ける、照明の明るさを調整するなど)。
- 見通しが立たない不安を解消するため、生活の流れを視覚的に提示する(スケジュールを貼るなど)。
- 成功体験を積み重ね、低下した自己肯定感を回復させる(得意なこと、好きなことを最大限に尊重する)。
4-3. 連携の輪:学校と家庭と医療・支援機関
ODとDDの両方に対応するためには、複合的な視点を持つ専門家との連携が不可欠です。
- 身体のケア: ODを専門とする医療機関(小児科、心療内科など)
- 特性の理解と心理的ケア: 児童精神科、発達支援センター、カウンセリング
学校と家庭が、これらの機関から得た「特性に関する適切な情報」を共有し、子どもにとって最もストレスの少ない環境を構築していくことが、結果としてODの症状改善、ひいては登校につながるのです。
まとめ:誰もが当事者になり得る問題として
起立性調節障害は、中学生の約10%にみられる、決して珍しくない事象です。その中に、発達障害という困難が重なっているケースがあるという事実は、現代社会が抱える大きな課題の一つと言えます。
「朝起きられない」という目に見える症状の背景には、自律神経の不調だけでなく、脳機能の特性による過度なストレスという二つの困難が隠れている可能性があります。
大切なのは、「怠けではない」という認識を、社会全体で持つことです。そして、ODとDDの複合的な困難を持つ子どもたちに対して、その特性を理解し、身体的・精神的な負荷を軽減するための適切な支援を届けることです。
この情報が、お子さんの「朝起きられない」という困難の本質を理解し、次のアクションを起こすきっかけとなれば幸いです。
ご相談・カウンセリングのご案内
- 子どもが朝起きられないのはなぜ?
- もしかして、発達特性も関わっている複合型?
- 環境調整って言うけれど、どうやってするの?
- 親である自分が辛すぎて行動に移せない…
- ただただ不安ばかりが襲ってくる…
このような思いを抱えておられる方もいらっしゃると思います。
そんな時は、ぜひご相談ください。
当事者家族として苦しんだ経験を持つカウンセラーが、あなたに寄り添い、学校やご家族との調整をサポートします。
「ひとりじゃないよ!」と寄り添っていきたいと思っています。
お気軽にご相談ください。
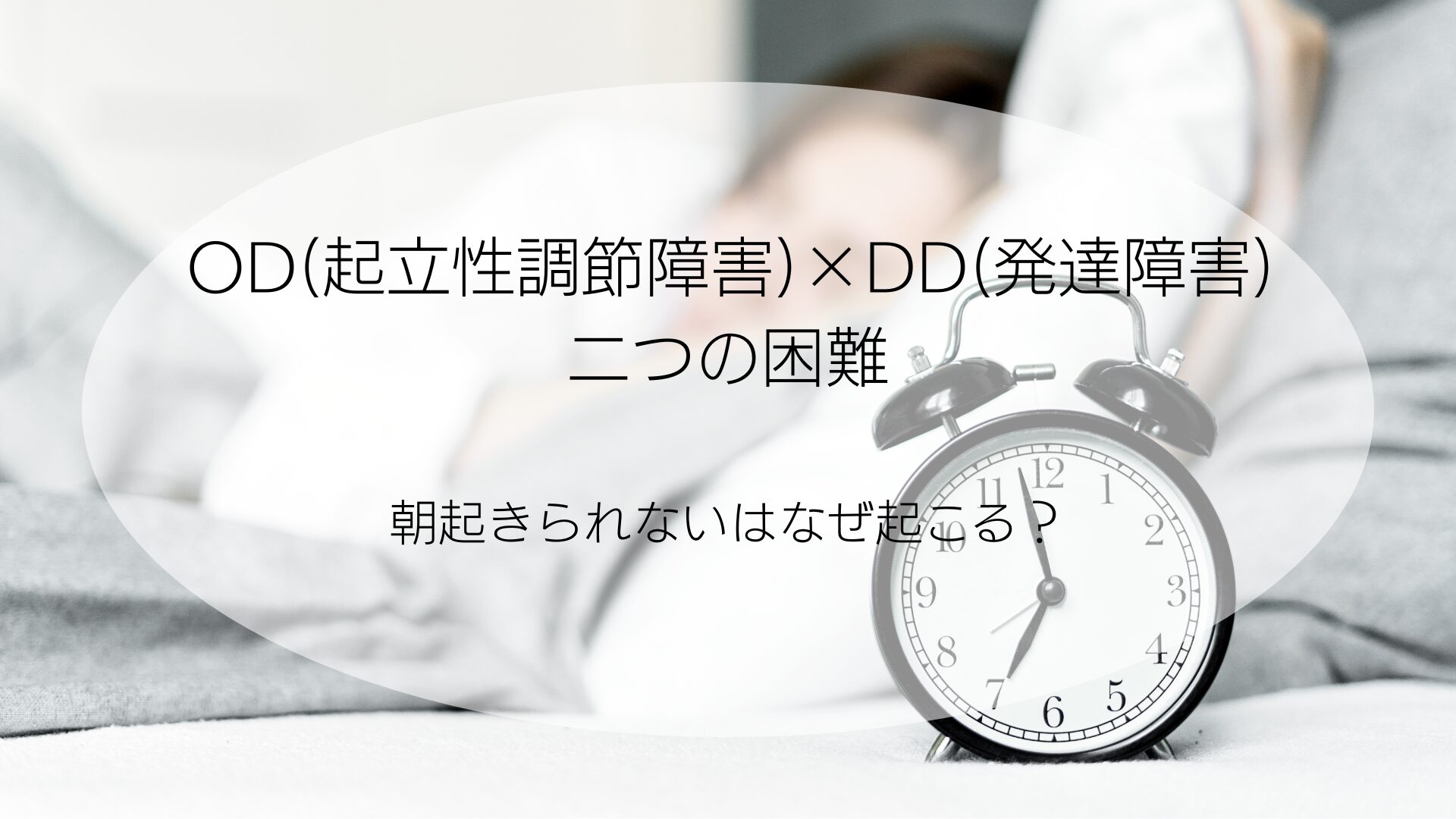
とは?-朝起きられないのは「怠け」じゃない_アイキャッチ-160x90.jpg)



コメント