近年、天候が安定しない日が多いように感じます。寒暖の差が激しかったり、一日の中で天気が急変したり…
「昨日は元気だったのに、今日は朝からベッドから出られない…」
起立性調節障害(OD)の子どもたちは、そんな“体調の波”を日々感じながら暮らしています。体調の浮き沈みがあることは決して特別なことではなく、多くの子どもに共通する現象です。
本記事では、その波がなぜ起こるのか、特に季節や天候の影響に注目して解説します。また、医学的な視点や過ごし方の工夫、親子でできる対話のヒントも紹介します。
「波」があるってどういうこと?
起立性調節障害(OD)とは、自律神経のバランスが崩れて、立ち上がったときに体がうまく順応できない状態です。代表的な症状には、以下のようなものがあります。
- 朝起きられない
- めまいや立ちくらみ
- 頭痛、吐き気、動悸
- 全身のだるさ、集中力の低下
多くの場合、午前中に症状が強く、午後にかけて軽くなる傾向がありますが、それも毎日一定ではありません。
ある日は比較的元気でも、次の日には動けなくなる。そんな「軽い日」「重たい日」が交互にやってくる――これがODの「波」です。
周囲からは、「さっきまで元気だったじゃない」と言われることもあるかもしれません。でもそれは本人のせいではなく、体の内側で起きているリズムの乱れなのです。
人によって出方が違う
ODの症状には個人差があります。
たとえば……
- 朝だけ起きられず、午後には元気になる子
- 夕方になると頭痛が強くなる子
- 一日中倦怠感が続く日がある子
- 周期的に数日間しんどくなる子
その「波」の周期にも違いがあり、週に一度調子が良くなる子もいれば、季節の変わり目に体調を崩しやすい子もいます。
実は、ODにもいくつかタイプがあり、体の中で起きている変化によって分類されます。医学的にはこのように細かく分けて考えられています。
| 分類 | 名称 | 主な特徴・診断基準 | 主な症状例 | 頻度・備考 |
|---|---|---|---|---|
| サブタイプ① | 起立直後性低血圧(OH) | 起立直後に血圧が急激に低下。回復まで20〜25秒以上かかる。平均血圧60mmHg未満で臓器虚血の恐れ。 | 立ちくらみ、めまい、失神など | 最も多いタイプ |
| サブタイプ② | 体位性頻脈症候群(POTS) | 起立3分後以降に心拍数が急増(+35〜45bpm以上)。血圧低下なし。 | 倦怠感、ふらつき、頭痛、動悸(自覚しない場合も) | 2番目に多い |
| サブタイプ③ | 血管迷走神経性失神(VVS) | 起立中に突然の血圧低下・脳虚血。失神を伴うことが多い | 意識が遠のく、突然倒れる | まれ/他のタイプと併発しやすく重症化あり |
| サブタイプ④ | 遷延性起立性低血圧(Delayed OH) | 起立直後は問題なし。3〜10分後に血圧が低下 | 徐々にふらつき、頭重感、疲労感 | まれ/鑑別は発症タイミングが鍵 |
| 分類外① | 脳血流低下型(起立性脳循環不全型) | 血圧・心拍は正常だが脳血流のみ低下。近赤外分光計で診断 | 立ちくらみ、集中力低下、頭重感 | 約15%のOD患者/診断には専用機器が必要 |
| 分類外② | 過剰反応型(Hyper Response型) | 起立直後に一過性の血圧上昇。自律神経の過反応が背景 | めまい、立ちくらみ、一時的ふらつき | 約15%のOD患者と推定 |
こうしたタイプにより、「午前中だけつらい人」もいれば、「夕方になるとだるくなる人」もいます。また、気温や湿度、気圧の変化に敏感に反応する人も多く、一人ひとりの波のリズムは違うのです。
周囲が「ずっと元気であること」を前提にすると、無理をさせてしまうことがあります。むしろ「波があるのが普通」と捉え、その子自身が「自分のパターン」を知っておくことが大切です。
気候や天候はどれだけ影響するの?
「雨の日はいつもよりつらそう」
「寒くなると、動けない日が増える」
よく聞かれる声です。
我が子の場合は、季節の変わり目や台風が発生したとき、天気の移り変わりが急な時に、辛そうな姿を目にしました。
ODの症状は、気温、湿度、気圧、日照時間など、環境要因にも強く影響されます。以下のような変化が関係しているといわれています。
どうして“低気圧の日”はつらくなるの?
低気圧は空気が薄くなり、体に酸素を取り込みにくくさせるだけでなく、血管を拡張しやすくすることで自律神経に影響を与えます。
この影響で、立ちくらみ・だるさ・頭痛などが強く出ることがあります。
気温と湿度もカギ
- 気温差が激しい日:寒暖差に体がついていけず、自律神経の調整に負担がかかる
- 湿度が高すぎる日:汗がうまくかけず、体温調整が難しくなり、脱力感が出やすい
- 冷え込む朝:血流が悪くなり、起きるのがよりつらくなる
- 日照時間の短さ:体内リズムが乱れ、朝起きづらくなる原因にも
これらが複雑に絡み合い、症状の軽重に影響を及ぼしているのです。
医学的に見る「なぜ波が起こるのか?」--自律神経のしくみと乱れ
自律神経は、体の無意識な働きを調整してくれる神経です。
たとえば、体温、血圧、心拍、消化などがその対象です。
- 交感神経:体を活動モードにする(心拍数を上げる、血圧を上げる)
- 副交感神経:体を休ませるモードにする(心拍数を下げる、消化を促す)
ODでは、この自律神経の切り替えがうまくいかず、特に立ち上がったときに血圧や心拍数の調整が乱れます。
ODの子が“ラクに過ごせる天気”とは?
比較的体調が安定しやすいのは、次のような気候です。
- 気圧が安定している晴れの日
- 春や秋の、寒暖差が小さい季節
- 湿度が50〜60%程度で、空気がこもっていない状態
- 室内外の温度差が少ない日
特に春や秋の中でも、天気が穏やかで気温が20度前後の日は、症状が軽くなる傾向にあります。
また、室内環境も重要です。エアコンの効いた部屋で一定の温度を保てるだけでも、症状が安定しやすくなることがあります。
「今日はつらいかも」――注意したい気候・天気
逆に、症状が重くなりやすいのは以下のような気候です。
- 低気圧が近づいている(台風・大雨の前後)
- 曇りや雨が続く日
- 湿度が高い梅雨の時期
- 真夏の蒸し暑さ、冬の冷え込み
- 一日の中で気温差が大きい日
特に梅雨から夏にかけては要注意です。湿度が高く、気温差が大きくなるこの時期は、自律神経が乱れやすく、倦怠感や立ちくらみ、頭痛などが強く出る子が多く見られます。
また、冬の寒さも油断できません。寒冷による血管収縮が原因で、血流が悪くなり、症状が強く出る場合もあります。
こうした日には、無理をせず、“「今日はがんばらなくていい日」”と受け入れることも大切です。
症状の「波」とうまくつきあうための対策
天候や季節の変化は避けられませんが、予測と備えをすることで、症状を軽減したり、悪化を防いだりすることができます。
以下のような対策が有効です。
規則正しい生活リズムを意識
毎日同じ時間に起き・寝ることで、体内時計が整いやすく自律神経の安定につながります。
ただし「起きられない日」を責めず、「今日は調子が悪いんだな」と受け止めることが大切です。
水分と塩分の補給をこまめに
ODでは血圧が低くなりがちなので、水分と塩分を意識してとることが推奨されています。朝起きた直後にコップ1杯の水を飲むことも効果的です。
天候を「見える化」する
気圧や天候の変化が体調に影響する人は、「頭痛ーる」などのアプリでチェックしておくと、心構えができます。
温度・湿度の管理
エアコンや加湿器・除湿器を使い、寒暖差の少ない環境を整えることで、体への負担を軽くできます。
外出予定を天気で調整する
体調が崩れやすい日は無理せずお休みを選択することも大切です。
上記をチェックリスト化してみました。
✅ 症状の波とうまくつきあうためのチェックリスト
- ⏰ 毎日同じ時間に起き・寝る
- 🧂 朝にコップ1杯の水+塩分をとる
- ☁️ 気圧・気温アプリで“見える化”
- 🌬 室温・湿度を安定させる
- 📅 外出予定を体調優先で調整
いかがでしょう?
今からでも取り組めそうなこと、ありますでしょうか?
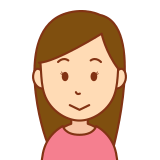
私自身も天候による不調が出ることが多いです。
そんなときは、子どもの主治医から教えていただいた漢方薬を服薬しています。
子どもは漢方が苦手なので、なかなか自分からは飲みませんが…(苦笑)
一例として、カウンセリングにてお伝えするこができますよ。
親ができる“そっと寄り添う一言”とは?
一番大切なのは、体調の変化を「気のせい」にしないことです。
「今日つらいのは、気圧のせいかもしれないね」
「この気温、体にはちょっとしんどいよね」
そんな風に、親が言葉にしてくれるだけで、子どもは「わかってもらえた」と感じ、自分の感覚に自信を持つことができます。
体調の波は、コントロールしきれないこともあります。でも「揺れても大丈夫」というメッセージを伝え続けることで、子ども自身の安心感につながります。
日記や体調記録アプリなどで、自分の体の波を「見える化」していくのもおすすめです。親子で一緒に取り組むことで、対話が生まれ、心の安心にもつながります。
まとめ
起立性調節障害の症状には、個人差もあれば、季節や天候による波もあります。
「波があるのがあたりまえ」とわかっていれば、自分を責めることなく、「今は休むとき」「今日はちょっと動けそう」と、体の声を聞きながら毎日を送ることができます。
天候や季節を完全にコントロールすることはできませんが、備えることはできます。
体調が安定しやすい工夫を続けながら、その子のペースを大切にできるとよいですね。
親子で一緒に「今日はどうだった?」と対話することで、心も少し軽くなるかもしれません。
ご相談・カウンセリングのご案内
「この子の体調の波に、どう向き合えばいいのかわからない」
「どう声をかければいいのかわからない」
「家庭の中でもギクシャクしてしまう」
「体調の波に一喜一憂してしまって、親の私がしんどくなることもある」
そんな声を、私はたくさん聞いてきました。
実際に私もそうでした。今でも迷いつつ辛いなと思うことがあります。
起立性調節障害の子どもに向き合う親御さんこそ、話せる場や安心できる支援が必要です。
しんどいのは、あなたのせいではありません。ひとりで悩まずご相談ください。
当相談室では、起立性調節障害のお子さんをもつ保護者の方へ、症状の理解、家庭でできる関わり方、親自身の心のケアなど、心の整理や対応の工夫をお手伝いし、個別にサポートしています。
オンラインでのご相談も可能です。
▼ご相談はこちらから
安心して話せる場所を、いつでもご用意しています。
(参考: 日本小児心身医学会 起立性調節障害ワーキンググループ)
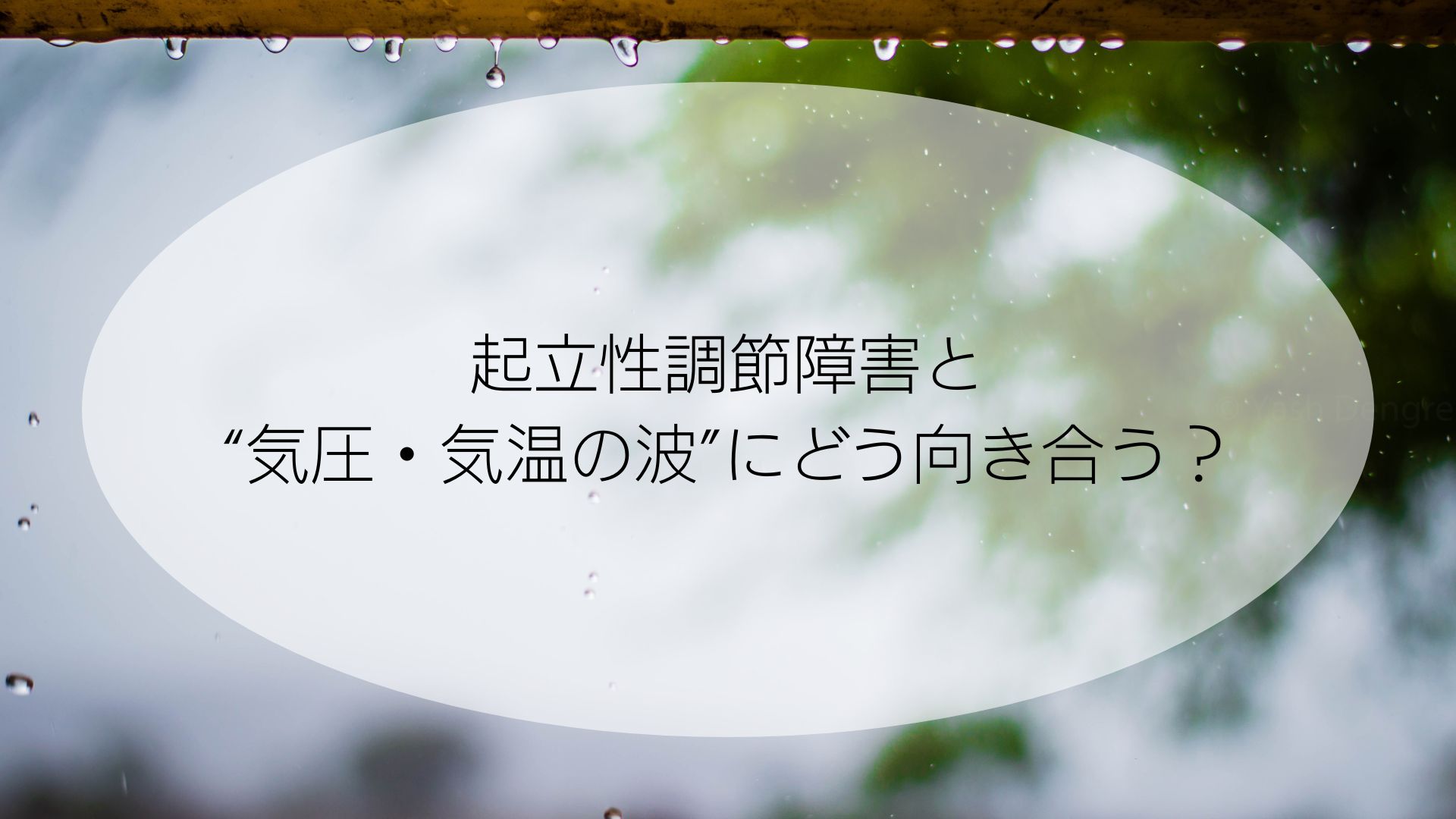


コメント